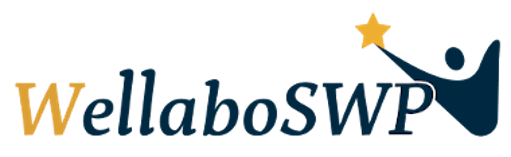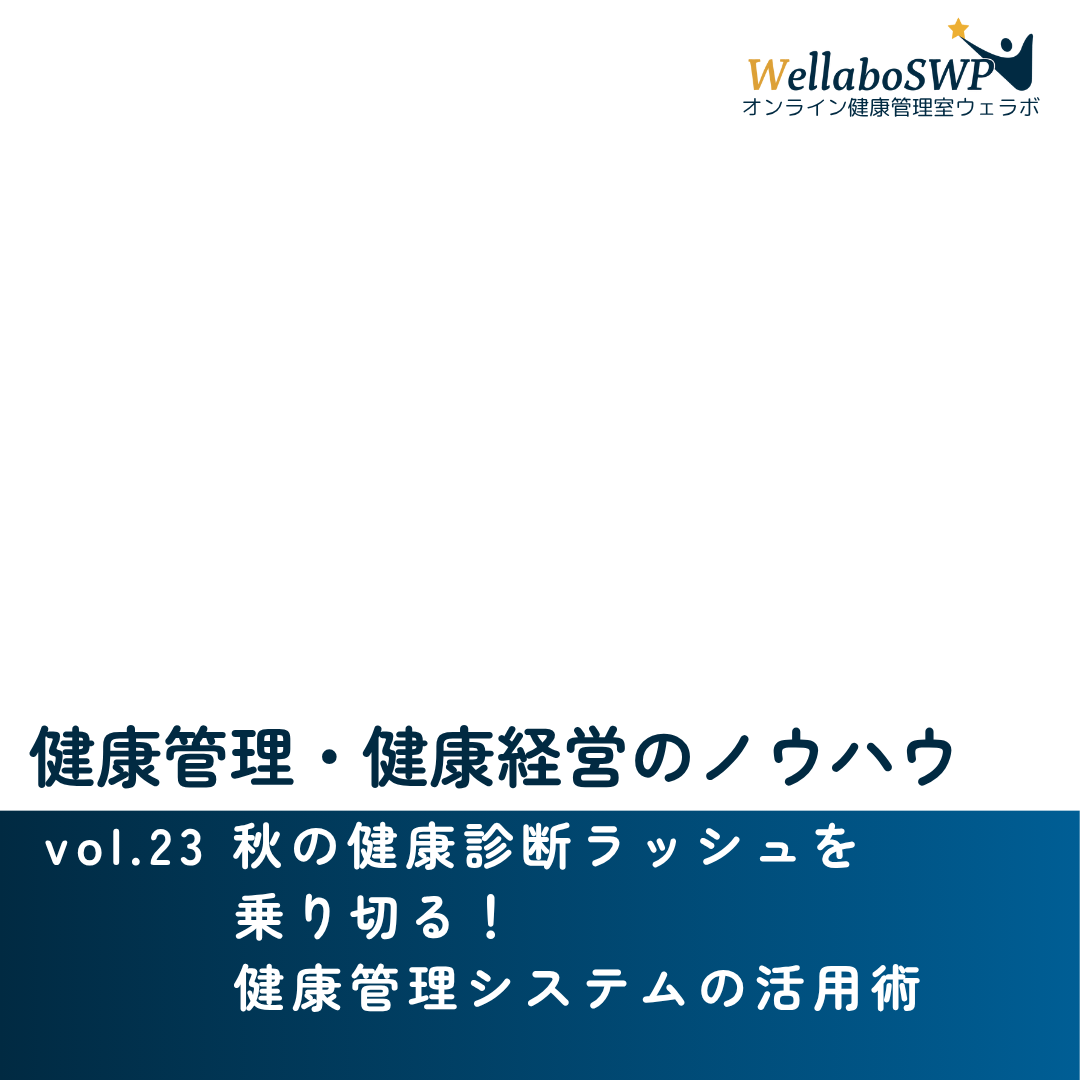介護施設経営に『健康管理』という視点を
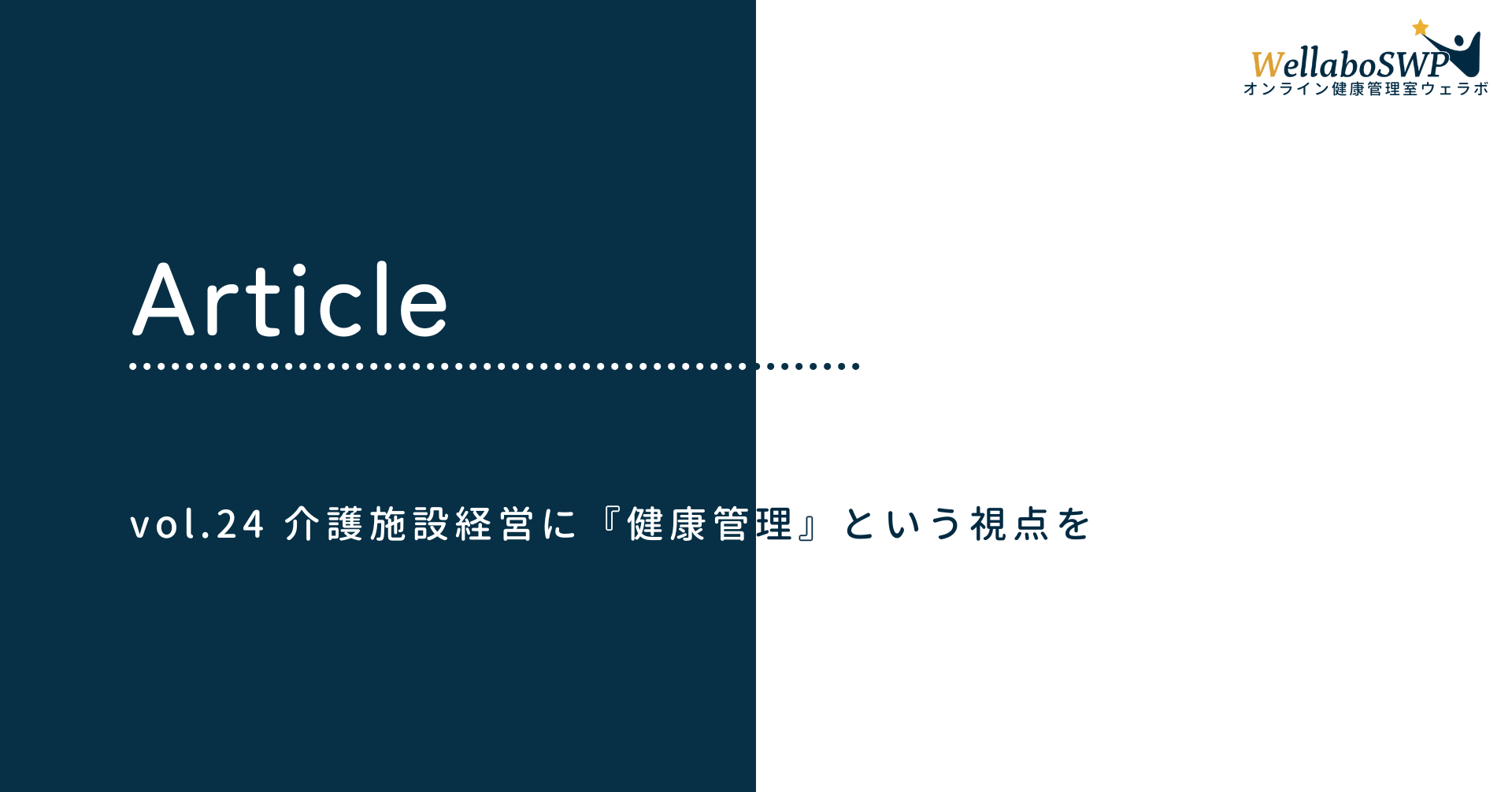
介護施設経営の現状
2024年度の介護事業者の倒産は179件で、介護保険制度開始以降で過去最多を記録しました。特に訪問介護が86件と全体の約半数を占め、小規模事業者を中心に淘汰が進んでいます。
その一方で、明るい兆しも見えています。介護職員の離職率は12.4%と2年連続で低下し、全産業平均の15.4%を下回る水準まで改善。人材不足が謳われる中で採用率も14.3%で、離職率を上回り人材は純増しています。

データから見る介護施設経営の現状
倒産件数は過去最多を記録
東京商工リサーチの調査によると、2024年度の介護事業者倒産179件のうち、訪問介護が86件(48.0%)と最も多く、次いで通所・短期入所が55件、有料老人ホームが17件でした。
倒産理由の74.3%を占めるのが「売上不振(販売不振)」です。利用者を十分に確保できず、介護報酬を得られない。人材紹介会社への依存で経費が膨らむ。こうした悪循環に陥った事業者が、競争に敗れて市場から退出しています。
倒産した事業者の特徴を見ると、資本金1,000万円未満が87.7%、従業員10人未満が83.2%、負債1億円未満が80.4%と、小規模・零細事業者が大半を占めています。
人材状況は着実に改善
人材確保の状況は、確実に改善しています。
公益財団法人介護労働安定センターの令和6年度調査によると、介護職員の離職率は12.4%と2年連続で低下。これは全産業平均の15.4%を3ポイントも下回る水準です。
採用面でも好転しています。採用率は14.3%で、離職率の12.4%を1.9ポイント上回りました。特に若年層の採用が好調で、20-24歳の採用率は31.4%、25-29歳は36.2%に達しています。
賃金改善も進んでいます。月給平均は248,884円で、前年度から3.1%増加。特に若年層では、20-24歳で5.8%増、25-29歳で5.0%増と大幅な賃上げが実現しています。
それでも、65.2%の事業所が従業員不足を感じており、人材確保の課題は依然として残っています。
特養の経営状況
特別養護老人ホームの経営状況を見ると、二極化の実態が浮かび上がります。
福祉医療機構の2023年度調査によると、サービス活動増減差額比率は従来型で1.6%、ユニット型で4.9%でした。前年度(従来型0.3%、ユニット型4.1%)からは改善していますが、赤字施設の割合は従来型で42.1%、ユニット型で31.1%に達しています。
つまり、黒字施設は収益を伸ばし、赤字施設は状況がさらに悪化するという格差が拡大しています。
成功要因について考える
では、この厳しい環境下で経営を改善している施設と、倒産に追い込まれる施設の違いは何でしょうか。
成功のヒントは以下の三点ではないでしょうか
①処遇改善への積極的な取り組み
複雑だった3つの処遇改善加算が2024年6月に一本化され、最大24.5%の加算率が設定されました。この新制度をいち早く理解し、適切に運用している施設は、職員の賃金を着実に引き上げ、人材確保で優位に立っています。
②生産性向上への投資
ICTや介護ロボットの導入により、業務効率化とサービスの質向上を同時に実現しています。ICT機器を導入した施設では、昼間の業務負担軽減効果を49.4%が実感し、夜間の業務負担軽減効果を44.6%が実感しています。
③職場環境改善
離職率が低い施設は、「有給休暇の取得をしやすい職場づくり」(実施率74.7%)や「人間関係が良好な職場づくり」(実施率72.0%)に積極的に取り組んでいます。
しかし、職場環境改善の中に、まだ多くの施設が十分に対応できていない重要な領域があります。それが「従業員の健康管理」ではないかと私たちは考えています。事実、介護労働安定センターの調査によると、「健康対策や健康管理の充実」を実施しているのは42.5%の施設にとどまります。従業員に「働き続けることに役立つこと」を聞いたところ、「定期健康診断の実施」がトップの53.8%であることからも、健康支援に関するニーズは確実にあるのではないかと考えられます。
「ケアする人をケアする」という経営視点
とても当たり前の話なのかもしれませんが、ケアする人自身が健康でなければ、質の高いケアは提供できません。また、介護の仕事は身体的にも精神的にも大きな負担がかかります。「身体的負担が大きい」と感じている従業員は24.6%、「健康面の不安がある」と答えた従業員も19.4%に上ります。精神的な負担の観点では、介護サービス職業従事者の精神障害による労災請求件数は、2014年の62件から2020年には136件へと2.2倍に増加しています。手厚い健康管理を行うことによる未然予防や早期発見・予防、重症化予防の余地は十分に残っているのではないでしょうか。「ケアする人をケアする」経営視点は、持続可能な介護施設経営の重要なポイントであると考えられます。
健康経営の採用への貢献
健康管理への投資は、採用活動においても効果を発揮します。「あの施設は従業員を大切にしている」という評判が広まれば、求人への応募が増えます。面接時に健康管理の取り組みを説明できることは、大きなアピールポイントになると考えられます。今なら競合施設との差別化にもなり得ると考えられます。また、離職率が低い施設では、既存職員が知人を紹介してくれるケースが増えます。人材紹介会社に高額な手数料を払わずとも、良質な人材を確保できるようになれば経営への貢献度は高いと言えます。
経営への効果
健康管理への投資は、短期的にはコストに見えるかもしれません。しかし、中長期的には確実にリターンをもたらします。というのも、従業員が健康であれば、欠勤が減り、業務の安定性が高まります。メンタルヘルス不調による長期休職も防げます。健康経営での文脈で言えば、不調によるパフォーマンス低下、いわゆるプレゼンティーズムの改善にもつながります。
何より、健康な従業員は良い雰囲気を作ります。その雰囲気は、利用者にも伝わり、利用者や地域にも選ばれる施設になるのではないでしょうか。そして、結果としてそのような職場には、優秀な人材も集まります。人材確保も楽になると考えられ、健康管理を起点としたポジティブな経営スパイラルが起こると言っても過言ではありません。
オンライン健康管理室ウェラボが実現した介護施設の事例
実際に従業員の健康管理に取り組み、変化を実現した支援事例があります。
社会福祉法人仁愛会様(職員220名)では、健康管理システムの導入により施設長の業務負担を削減し、離職率の大幅改善を実現しました。最も重要だったのは、「ケアする人もケアを受ける」という組織風土の構築です。第三者による専門的な健康管理を導入することで、従業員が安心して健康相談できる環境が整いました。
介護施設では、従業員が利用者のケアに専念するあまり、自分自身の健康を後回しにしがちです。しかし、ケアする人自身が健康でなければ、質の高いケアは提供できません。
仁愛会様の事例は、健康管理への投資が離職率改善という形で確実に成果につながることを示しています。
仁愛会様の詳細な導入事例についてはこちらをご覧ください
まとめ
いかがでしたでしょうか。今後も介護需要は増える中で選ばれる介護施設であり続けるためには、「ケアする人をケアする」健康管理体制を構築することは一つの解であると考えられます。産業医選任義務のない施設や、選任していたとしても従業員の健康支援のニーズに十分に応えることのできていない介護施設もまだ多くあります。オンライン健康管理室ウェラボはそのような施設に有効な支援サービスです。
オンライン健康管理室ウェラボの紹介はこちらをご覧ください
参考文献・出典
公益財団法人介護労働安定センター「令和6年度介護労働実態調査結果の概要について」(2025年7月公表)
東京商工リサーチ「2024年度の介護事業者の倒産」(2025年7月発表)
福祉医療機構「2023年度特別養護老人ホームの経営状況について」(2024年3月公表)
厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」(2024年8月公表)
厚生労働省「精神障害に関する事案の労災補償状況」(2020年度)
厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」(2024年2月公表)
執筆・監修
WellaboSWP編集チーム
「機能する産業保健の提供」をコンセプトとして、健康管理、健康経営を一気通貫して支えてきたメディヴァ保健事業部産業保健チームの経験やノウハウをご紹介している。WellaboSWP編集チームは、主にコンサルタントと産業医・保健師などの専門職で構成されている。株式会社メディヴァの健康経営推進チームに参画している者も所属している。