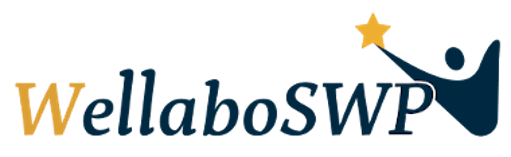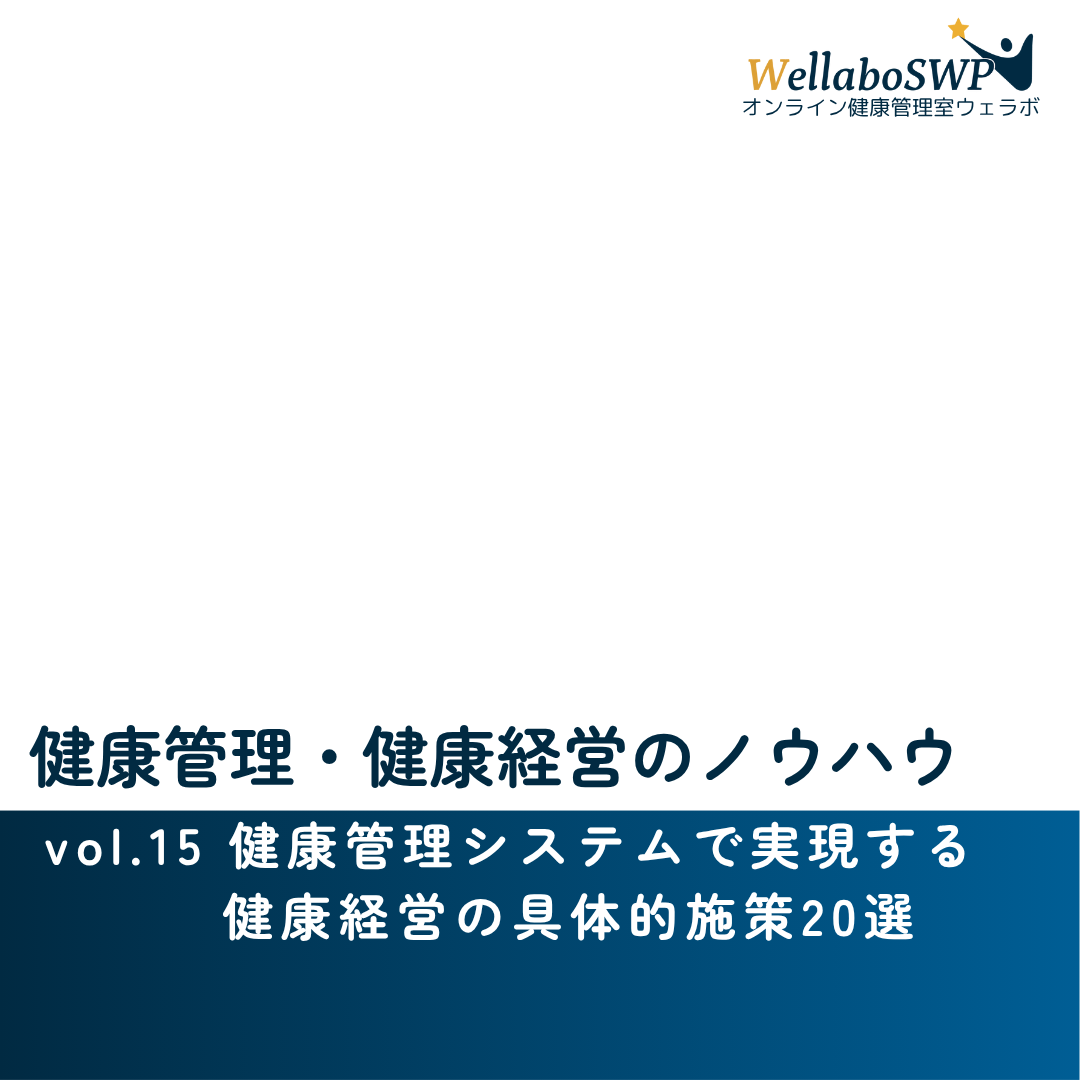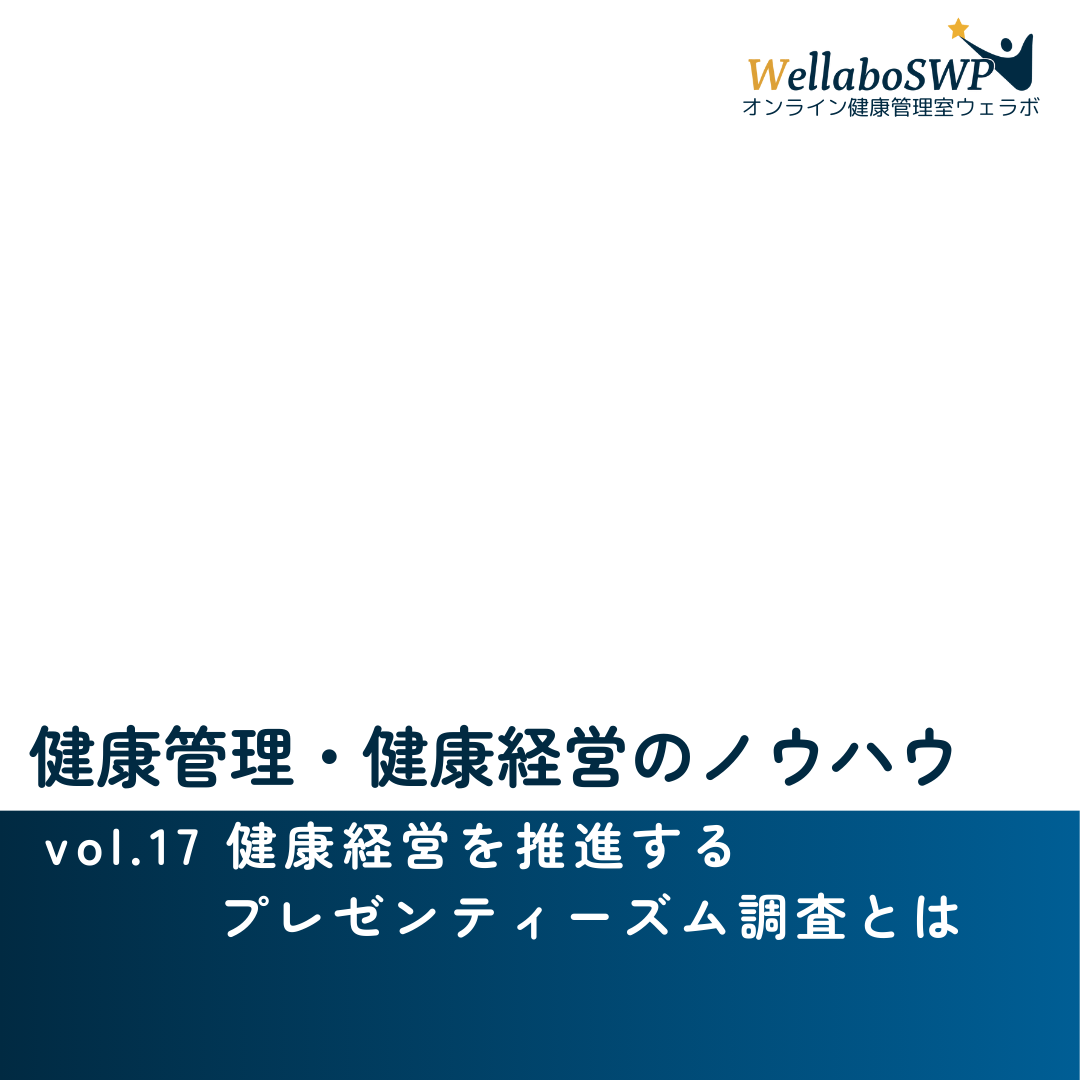健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定申請の変更点を徹底解説!中小企業の健康経営担当者が押さえるべきポイント
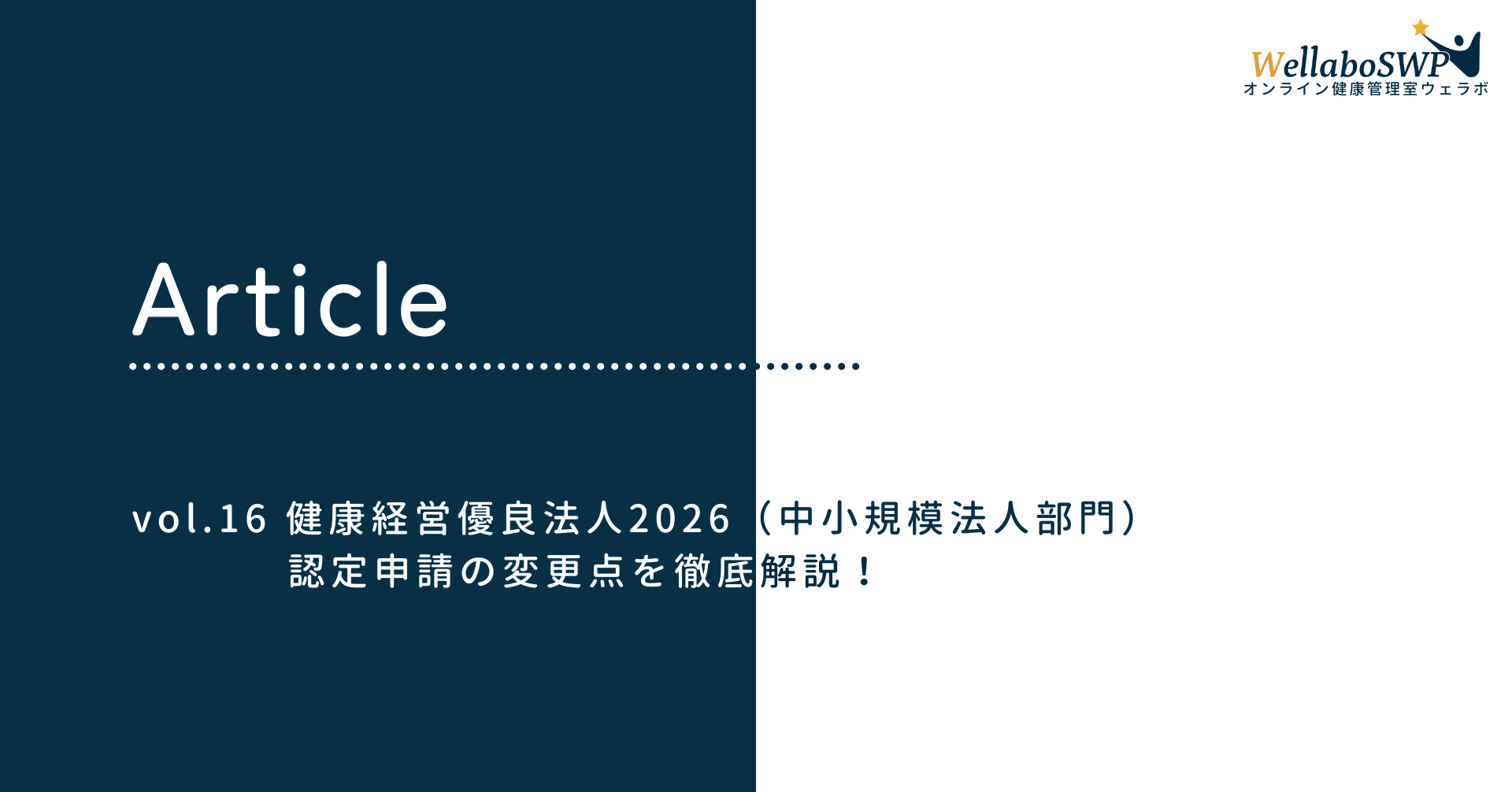
2025年7月18日に開催された第3回健康経営推進検討会で、健康経営優良法人2026(中小企業法人部門)認定申請書(素案)が公表され、前年度から改訂される項目も明らかになりました。本記事では、主要な変更点と対応のポイントを詳しく解説します。
1. 多様な法人・組織体に対応した認定制度へ
健康経営優良法人2026から、自治体も申請可能になりました。自治体については、首長部局と指揮命令系統が異なる教育委員会などの各種委員会単位からの申請を認めることになり、それぞれの組織の実情に応じた健康経営の推進が可能となりました。健康経営度調査の申請区分にも、地方公共団体向け特例の記載が追加されています。
ポイント
- 民間企業だけでなく、公的機関も健康経営の取り組みに参加
- 首長部局、教育委員会、その他の委員会など、独立した組織単位での申請が可能
- 地域・社会全体での健康経営普及が加速
- 現在、18自治体(前年度から9自治体増加)が既に健康経営優良法人2025大規模法人部門に認定されており、今後さらなる増加が見込まれる
2. 認定要件の主な変更点
2-1. メンタルヘルスに関する認定要件項目名変更
変更内容:
- 認定要件項目の名称を「心の健康保持・増進に関する取り組み」に変更
- メンタルヘルスの取り組みが従業員自身の能力発揮につながることも踏まえた変更
この名称変更の背景には、「メンタルヘルス不調者への対応」という従来の表現が、問題が発生してからの事後対応を想起させることがあります。新たな名称では、従業員の心の健康を積極的に保持・増進し、一人ひとりが能力を最大限に発揮できる職場環境づくりを目指すという、より前向きなアプローチが強調されています。
心の健康保持・増進に関する取り組み
評価設問:Q28
この変更により、企業は以下のような予防的・促進的な取り組みをより積極的に実施することが期待されます:
- ストレスチェックの実施と職場環境改善への活用
- メンタルヘルス研修の定期的な実施
- 相談窓口の設置と利用促進
- ワーク・エンゲイジメント向上のための施策
- レジリエンス強化プログラムの導入
また、Q28SQ1では心の健康に関するデジタルツールの活用という設問が追加されました。本設問は評価には使用されませんが、どのようなツールがどの程度使われているかという集計結果に注目しています。
2-2. 就業者の質的変化を踏まえた認定要件の項目追加
就業者における性差・年代が変化する中で、女性や高齢従業員が働きやすい職場づくりを進めることの重要性が高まっている現状を踏まえ、認定要件の小項目「健康経営の実践づくりに向けた工台づくり」の評価項目を見直し、女性の健康への対策と高齢従業員への対策を「性差・年代を踏まえた職場づくり」として、評価項目に追加されました。
① 女性の健康保持・増進に向けた取り組み(配置変更)
評価設問:Q21
女性特有の健康課題への理解と支援体制の構築が重視されています。
主な評価ポイント:
- 検診・健診支援:婦人科がん検診、骨密度測定等への金銭補助や就業時間認定
- 相談・支援体制:女性の健康専門の相談窓口設置、産業医・婦人科医師との連携
- ライフステージへの対応:妊娠・出産、更年期、月経随伴症状(PMS等)への配慮
- 職場環境整備:女性専用休憩室の設置、生理休暇を取得しやすい環境づくり
- 教育・啓発活動:女性の健康関連課題に関する研修・セミナーの実施
② 高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み(新規追加)
評価設問:Q22
厚生労働省「エイジフレンドリーガイドライン」等を踏まえ、60歳以上の高年齢従業員に対する包括的な支援が評価されます。
主な評価ポイント:
- 職場環境の物理的改善:転倒防止、視覚・聴覚負担の軽減のための設備・装置の導入
- 柔軟な勤務制度:短時間勤務、勤務日数の調整、テレワーク等の選択制度
- 健康管理・予防対策:体力測定、フレイル・ロコモチェック、運動習慣・食生活改善セミナーの実施
- リスク管理:ヒヤリハット事例の収集と危険マップの作成・周知
- 再雇用者への配慮:定年後再雇用者向けの病気休暇制度の整備
これらの取り組みにより、性別や年齢に関わらず、すべての従業員が健康で働きやすい職場環境の実現を目指します。
2-3. 「育児・介護と仕事の両立支援」を認定要件に追加
昨年度、中小規模法人部門申請書のアンケート項目であった「育児・介護と仕事の両立支援」が、2026年度から認定要件の選択項目に正式に追加されました。これにより、多様な家族形態やライフステージに対応した職場環境の整備がより重要になります。
① 仕事と育児の両立支援
評価設問:Q17
重要:法定の範囲(育児・介護休業法)で定められている以上のことを行っている場合のみ評価対象
主な評価ポイント:
- 休暇・休業制度の充実:法定を超える育児休業期間の設定、看護休暇の有給化
- 柔軟な勤務制度:時短勤務、フレックスタイム、在宅勤務など、法定以上の制度整備
- 経済的支援:保育施設の整備・補助、ベビーシッター費用補助
- 復職支援:育児休業中の情報提供、復職前面談の実施
- 男性の育児参加促進:男性の育児休業取得推進、配偶者出産休暇の有給化
② 仕事と介護の両立支援
評価設問:Q18
重要:法定の範囲(育児・介護休業法)で定められている以上のことを行っている場合のみ評価対象
主な評価ポイント:
- 情報提供・相談体制:介護セミナーの開催、専門相談窓口の設置
- 柔軟な勤務制度:介護のための短時間勤務、在宅勤務(法定を超える期間・回数)
- 経済的支援:介護サービス利用補助、介護休業の有給化
- 職場の理解促進:管理職向け研修、介護経験者の体験共有の場の設置
- 継続就業支援:介護による離職防止のための個別支援計画策定
注意事項:
- 単に法定の制度があるだけでは評価対象になりません
- 法定を超える取り組みの実施状況を証明できる資料の保管が必要です
- 2025年4月1日から段階的に育児・介護休業法が改正されているため、最新の法定基準を確認の上、それを超える取り組みを実施してください
2-4. 認定要件数の変更
中小規模法人部門の認定に必要な選択項目数が以下のように変更されました:
- 「高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み」の追加
- 「育児・介護と仕事の両立支援」の追加
- 15項目中7項目から17項目中8項目に変更
3. 新たに追加された評価項目
3-1. 高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み(Q22)
前述「2-2. 就業者の質的変化を踏まえた認定要件の項目追加」で詳述した通り、60歳以上の高年齢従業員に対する包括的な支援が新たに評価項目として追加されました。
3-2. 育児・介護と仕事の両立支援(Q17-18)
前述「2-3. 「育児・介護と仕事の両立支援」を認定要件に追加」で詳述した通り、法定を超える取り組みのみが評価対象となる新たな認定要件として追加されました。
3-3. 健康経営推進方針と目標、KGI・KPIの定義の整理(Q37)
評価設問:Q37 健康経営の方針(健康宣言等に関する経営トップの考えや健康経営を通じて何を実現したいのか)
健康経営の方針について、従業員に対して発表・定期的に通達している取り組みが評価されます:
- 経営トップ自身が朝礼やミーティングで定期的に伝達している
- 経営トップ自身が管理職に対して研修等を通じて定期的に伝達している
- 経営トップが発信したメール等でのメッセージが、毎年1回は必ず従業員に送信されている
- 健社内の健康経営の方針を目部署の周知方法に記しているところに伝達している
重要: 健康経営の推進方針と目標に関する取り組みが、よりKGI(経営層の健康経営への意欲を示すもの)とKPI(測定可能なアウトプット指標)を明確にすることで、PDCAサイクルの実効性を高めることが求められています。
3-4. 組織全体に影響する効果検証(Q39)
評価設問:Q39 健康経営の推進が健康風土醸成に向けて企業の健康風土の醸成状況や変化を把握しています
企業の健康風土を測定・評価する具体的な取り組みが新たに評価されます:
- アンケート等で自社の健康経営の推進方針、目標に対する従業員の認知・理解度の変化から把握している
- アンケート等で自社の健康経営推進に対する満足度の変化から把握している
- 従業員間におけるコミュニケーション量・頻度の変化から把握している
- アンケート等で職場の人間関係の変化から把握している
- 従業員と経営層における健康経営に関するコミュニケーション量・頻度の変化から把握している
- 食生活・運動習慣など生活習慣全般に対する健康意識・知識の変化から把握している
- 上司や同僚からのサポート状況の変化をヒアリング等で把握している
- 外部評価等に対して、自社の組織活性化の状況の変化をヒアリング等で把握している
3-5. その他の重要な追加・変更項目
⑨ プレコンセプションケアの認知と取組状況
プレコンセプションケアについて、企業において取組が意義を追加し、具体的に企業で実施している取り組み内容を確認できるようアンケート設問・選択肢を修正。中小規模法人については、認知を問うアンケートを新設。
⑩ 多様な働き方をする労働者への健康経営の広がり(Q51)
個人事業者等に対する健康経営のあり方を検討するため、個人事業者等(契約関係の労働についての労働時間が週40時間を超えた場合における超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働を提供しています)に対する健康支援の状況を問うアンケートを新設。
主な評価内容:
- 過重労働による健康障害を防止するような配慮を行っている
- 過重労働による感知の看護が認められる個人事業者等から求めがあった場合に、医師による面談を受ける機会を提供している
- 個人事業者等の心の健康不調への対応に配り組んでいる
- 安全衛生教育や健康診断に関する支援の提供を行っている
- 健康診断の受診に要する費用の全部または一部を負担するよう記慮している
- イベント等の自社の健康経営の取り組みについて、取引先の個人事業者から参加も募っている
4. ブライト500認定基準の改訂
4-1. 評価ウェイトの変更
| 評価項目 | 旧ウェイト | 新ウェイト |
| 適合項目数 | 6 | – |
| 経営者・役員の関与の度合い | 2 | 2 |
| 健康経営の組織への浸透に向けた取り組み | – | 1 |
| 健康経営のPDCAに関する取り組み状況 | 8 | 3.5 |
| 健康経営の推進による企業の健康風土の把握 | – | 2 |
| 自社からの発信状況 | 3 | 1 |
| 外部からの依頼による発信状況 | 1 | 0.5 |
4-2. 新設問の追加
① 健康経営ガイドブックの認知状況(Q35)
評価設問:Q35 健康経営ガイドブック(2025年3月版)について知っていますか
注意:本設問への回答はブライト500・ネクストブライト1000の選定には使用しません。
健康経営の定義や健康投資による効果、実践手順等を取りまとめた健康経営ガイドブックの認知度を調査する設問です。今後の健康経営施策の普及・啓発活動の参考として活用されます。
② 健康経営の推進における経営層の関与(Q36)
評価設問:Q36 健康経営の推進に関して、経営者・役員が関与している内容
経営層の健康経営への関与度を多面的に評価する重要な設問です。
主な評価ポイント:
- 推進方針への関与:健康経営のビジョン・目標・KGIの設定における経営層の関与
- 組織体制への関与:人材登用、組織整備、予算措置等における経営層の意思決定
- リーダーシップの発揮:経営者自身の施策参加、推進状況の把握、効果検証への参画
重要: 特にKGI(経営課題に紐づく目標達成指標)の明確化が求められ、生産性や財務関係の指標等、健康経営の目標達成状況を測る具体的な指標の設定が必要です。
③ 健康経営推進方針の発信と浸透(Q37)
評価設問:Q37 健康経営の方針(健康宣言等に関する経営トップの考えや健康経営を通じて何を実現したいのか)
変更点: 従来の「健康宣言の発信」から、より具体的な「経営トップの考えと実現したいビジョン」の発信へと評価の視点が深化しました。
主な評価ポイント:
- 経営トップによる直接的な伝達(朝礼、ミーティング、研修等)
- 定期的なメッセージ発信(年1回以上)
- 組織全体への浸透方法の明確化
④ 健康経営のPDCAサイクル強化(Q38)
評価設問:Q38 健康経営のPDCAに関する取り組み状況
変更点: PDCAサイクルの実効性をより重視し、具体的な改善活動の実施状況を評価する内容に変更されました。
主な評価ポイント:
- 定期的な評価・検証の実施
- 評価結果に基づく改善計画の策定と実行
- 次年度計画への反映プロセスの確立
⑤ 健康風土の醸成状況の把握(Q39)
評価設問:Q39 企業の健康風土の醸成状況や変化の把握方法
変更点: 新設問として、健康経営の推進が組織文化・風土にどのような影響を与えているかを定量的・定性的に把握することが求められるようになりました。
主な評価ポイント:
- 従業員の認知・理解度、満足度の変化測定
- コミュニケーション量・質の変化把握
- 健康意識・行動変容の評価
- 組織活性化指標による効果測定
これらの新設問により、ブライト500認定においては、健康経営の取り組みをより戦略的・体系的に推進し、その効果を客観的に把握・改善していくことが重視されています。
まとめ
健康経営優良法人2026の認定要件は、より包括的で実効性の高い健康経営の実現を目指す内容となっています。特に中小企業においては、限られたリソースの中で効率的に取り組みを進める必要があります。
成功のカギは早期の準備開始です。 今回の変更点を踏まえ、自社の現状を把握し、計画的に取り組みを進めていきましょう。健康経営は単なる認定取得のためではなく、従業員の健康と企業の持続的成長を実現するための重要な経営戦略です。
申請期限は2025年10月17日(金)17時です。余裕を持って準備を進め、より良い健康経営の実現を目指しましょう。
本記事は2025年8月6日時点の情報に基づいています。最新情報は経済産業省および健康経営優良法人認定事務局のウェブサイトでご確認ください。
執筆・監修
WellaboSWP編集チーム
「機能する産業保健の提供」をコンセプトとして、健康管理、健康経営を一気通貫して支えてきたメディヴァ保健事業部産業保健チームの経験やノウハウをご紹介している。WellaboSWP編集チームは、主にコンサルタントと産業医・保健師などの専門職で構成されている。株式会社メディヴァの健康経営推進チームに参画している者も所属している。