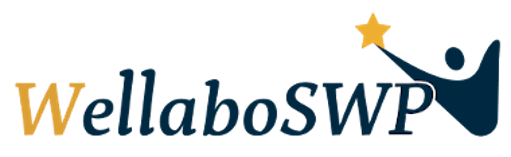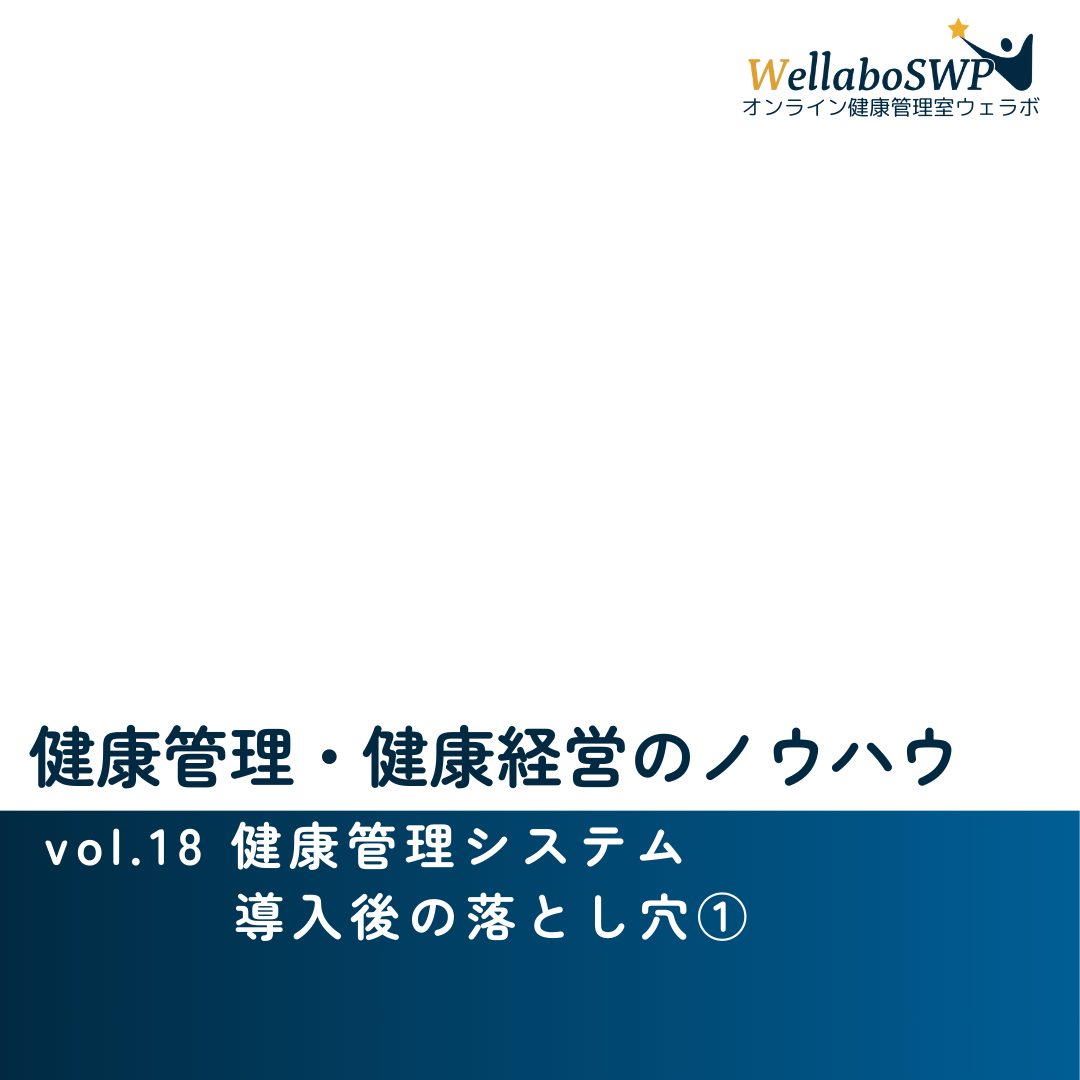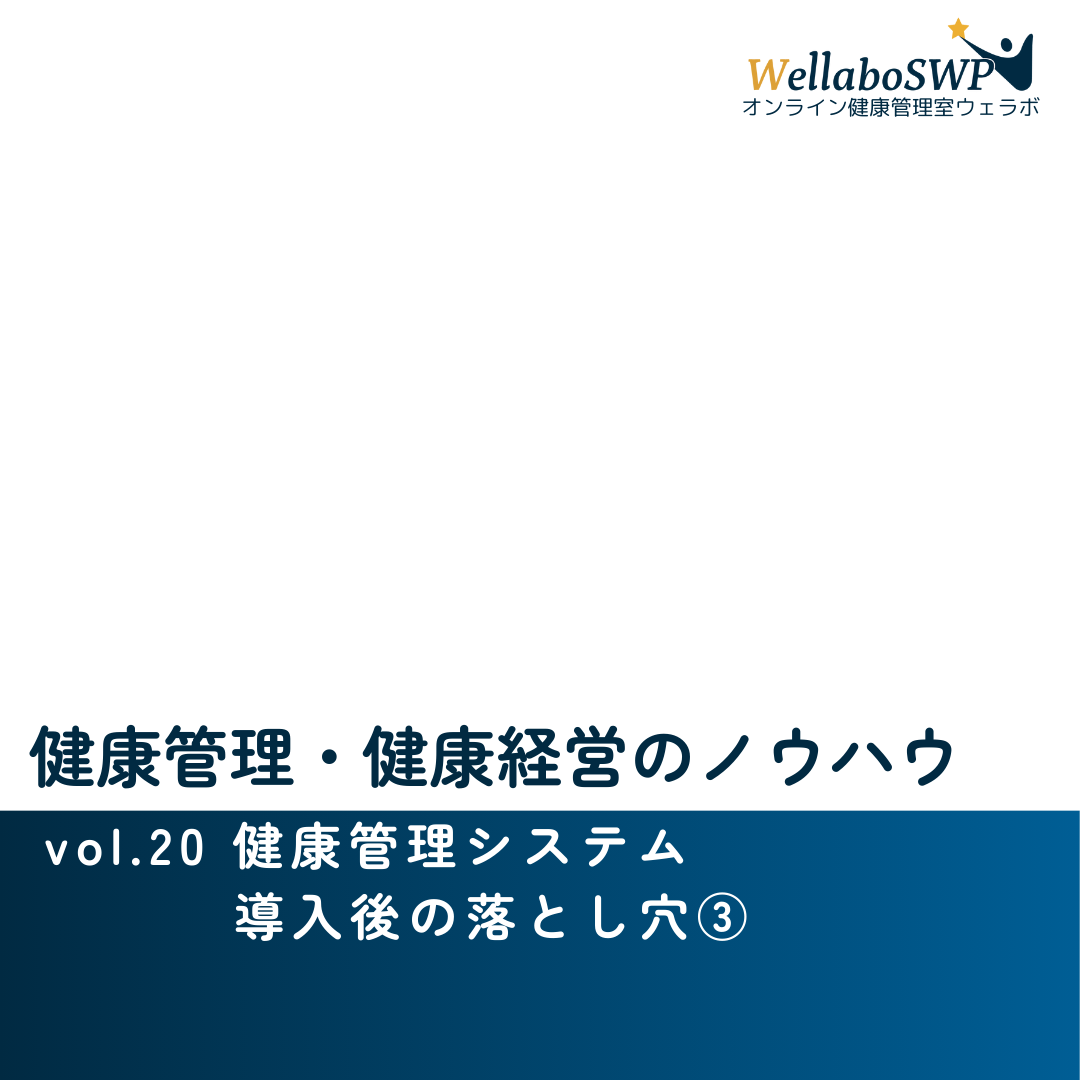健康管理システム導入後の落とし穴② ストレスチェック編

健康管理システムの導入を検討している、または既に導入したもののストレスチェック機能で期待した効果を得られずに悩んでいる企業担当者の方へ。本シリーズでは、健康管理システムの設計者・開発者の視点から、導入後によくある問題とその解決策を解説します。
第1回の「健康診断結果管理編」では、健診データの取得・管理に関する課題を取り上げました。第2回となる今回は、2028年に中小企業でも義務化が予定されているストレスチェック機能に焦点を当て、システム化で見落としがちな4つの運用課題をお伝えします。
ストレスチェック義務化に関する記事はこちら

なぜストレスチェックのシステム化で問題が起きるのか
ストレスチェックは、2015年から従業員50人以上の事業場で義務化された制度です。近年、健康管理システムの普及に伴い、従来の外部委託による紙ベースでの実施から、システム内でのWeb実施に移行する企業が増加しています。現在でも紙とWebの両方式が並存している状況ですが、システム化による効率性とデータ活用の利便性から、Web化を検討する企業が増えています。
しかし、ストレスチェックのシステム化は、健康診断結果管理とは異なる特有の課題を抱えています。ストレスチェックは「従業員が直接回答する」「個人情報保護への配慮が重要」「集団分析による職場環境改善が目的」といった特徴があるため、単純にシステムに移行するだけでは思わぬ落とし穴に陥ってしまうのです。
特に、2028年頃に予定されている50人未満の事業所への義務化拡大を見据えると、これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることが重要です。システム化を成功させることで、法令遵守の確実な実現と従業員の健康管理の向上を両立させ、企業の健康経営推進に大きく貢献することができます。
落とし穴1:ITリテラシー格差による受検率低下問題
紙からWebへの移行で起こる受検者の脱落
ストレスチェックを紙ベースからWebベースに移行する際、最初に直面するのがITリテラシーの格差による受検率の低下です。特に、普段パソコンやスマートフォンを業務で使用しない従業員が多い職場では、Web画面での回答に大きな不安を感じることがあります。
典型的な問題
- 「パスワードがわからない、入力方法がわからない」
- 「画面のどこをクリックすればいいのかわからない」
- 「途中で画面が止まってしまい、最初からやり直しになった」
- 「スマートフォンで回答しようとしたが、画面が小さくて見えない」
これらの問題により、従来(特に従来紙で実施していた場合)より受検率と比較して低下が見られることがあります。特にITに不慣れな従業員の多い職場では、この傾向が顕著に現れることがあります。
ハイブリッド実施による運用の複雑化
ITリテラシーの問題を解決するため、「Web回答を基本とし、必要な従業員のみ紙で実施」というハイブリッド方式を採用する企業があります。一見すると合理的な解決策に思えますが、実際の運用では以下のような問題が発生します。
運用上の課題
- どの従業員を紙対象にするかの判断基準が曖昧
- 紙回答者への個別対応による担当者の業務負荷増大
- 実施期間の延長による全体スケジュールへの影響
対策:段階的移行とサポート体制の構築
事前準備による解決アプローチ
- システム導入の1〜2ヶ月前に操作説明会を実施
- 実際の画面を使ったデモンストレーションの提供
- 操作方法を解説した動画マニュアルの配布
- 各事業所に操作サポートのできる人材を確保
- 操作に不安がある従業員向けの個別サポート時間の設定
技術的な対策
- シンプルで直感的なUI設計のシステム選定
- 多言語対応や音声ガイダンス機能の活用
- 回答途中での保存機能による「やり直し」ストレスの軽減
- モバイル対応の徹底とレスポンシブデザインの確認
落とし穴2:紙・Web混在時のデータ統合困難
データ化の隠れたコストと時間
ハイブリッド実施を行う場合、紙で回答された分を電子データ化する作業が必要になります。この作業は、内製で行うか外部に委託するかによって大きくコストと担当者が変わります。
内製でのデータ化の課題
- 手書き文字の判読困難
- 回答の抜け漏れや複数選択のエラー対応
- 個人情報を扱うことによる担当者の精神的負担
- データ入力ミスによる分析結果への影響
外注でのデータ化の課題
- データ化作業の追加コスト発生
- 外部業者への個人情報提供に伴うセキュリティリスク
- 外部業者の作業プロセスとシステムの統合がさらに困難
- データ品質のコントロールが困難
システム側の統合機能不足
健康管理システムでは、Web回答と紙回答の統合が技術的に困難な場合があります。特に以下のような問題が発生しがちです
システム統合の課題
- 紙回答分の手動入力によるデータ形式の不整合(外注した場合でも)
- Web回答と紙回答での回答者の重複チェックができない
- 集計結果の信頼性に対する疑問
- 分析レポートの生成エラーや不完全な結果
対策:統合を前提としたシステム設計
システム選定時の確認事項
- 紙・Web混在実施への対応機能の有無 (紙の運用実施も含めて)
- データ統合時の重複チェック機能(そもそも外部データを取り込めるかも含めて)
- 手動データ入力時のエラーチェック機能
- 統合後の分析精度を担保する仕組み
運用設計での対策
- 可能な限りWeb実施に統一する方針の徹底(最初は難しくても段階的には統一)
- 紙実施対象者を最小限に絞り込む基準の明確化
- データ統合作業の責任者と手順の事前決定
- 統合後のデータ品質確認プロセスの確立
落とし穴3:「分析のための分析」に陥る過剰解析
職場環境改善という本来目的の見失い
健康管理システムによるストレスチェックでは、多角的な分析が可能であることが多いです。年代別、部署別、役職別、勤続年数別など、様々な切り口での分析結果を簡単に出力できるため、つい「せっかくだから色々な分析をしてみよう」という発想に陥りがちです。
しかし、ストレスチェックの集団分析は、職場環境の改善を目的として実施するものです。つまり、分析は職場環境改善のための手段であって、職場環境の改善に利用することのできない切り口で分析をしてもその後につながりません。(筆者は組織・部署レベルの分析を丁寧に行うことを推奨しています)
よくある過剰分析の例
- 10人未満のグループでの分析(個人が特定されてしまうリスクがある)
- 改善施策につながらない項目への過度な着目
- 年1回の実施にも関わらず、過度に詳細な分析による担当者の負担増大
- 分析結果を配布したものの、受け取った管理職等が内容を理解できず放置される
分析結果の解釈スキル不足による混乱
多角的な分析が可能になると、担当者は大量の分析結果と向き合うことになります。しかし、これらの結果を正しく解釈し、具体的な職場環境改善につなげるためには、産業保健に関する専門知識が必要です。
解釈不足による問題の例
- 現場の実態を把握しないまま結果を問題として捉えてしまう
- 内容が難しく現場担当者が理解できない
- 他部署との比較による不要な競争意識の醸成
- 改善施策の優先順位を適切に判断できない
対策:職場環境改善を目的とした分析設計
分析の基本方針の確立
- 分析結果から具体的な改善アクションにつなげることを前提とした分析項目の選定
- 「なぜこの分析を行うのか」「この結果から何を改善するのか」を明確化
- 分析結果の解釈について産業医や保健師等の専門家による支援体制の構築
- 職場環境改善の実施可能性を考慮した現実的な分析範囲の設定
効果的な職場環境改善の進め方
- 課題仮説の設定:事前に想定される職場の課題を明確化
- 目的に応じた分析実施:仮説検証に必要な分析のみを実施
- 専門家による結果解釈:産業医・保健師等による結果の正しい解釈
- 参加型改善策検討の実施:
-
- 結果説明会の実施
- 管理職・従業員参加型での環境改善検討(職場のレベル感に応じて参加者を選定)
- 類似業務を行っている部署での好事例を活用した意見交換
- 産業医や保健師を交えた職場環境改善策の具体的検討
- 効果測定の計画:次回実施時の比較検証方法の事前設計
落とし穴4:部門間の連携不足による二重運用問題
健康診断部門とストレスチェック部門の分離による弊害
多くの企業では、健康診断の管理とストレスチェックの実施をそれぞれ別部門が担当することがあります。この組織体制において、健康診断管理部門主導で健康管理システムを導入した場合、思わぬ問題が発生することがあります。
典型的な問題のケース
健康診断管理部門がシステム導入を主導し、健康診断結果管理の効率化を目的として健康管理システムを導入しました。このシステムにはストレスチェック機能も含まれていたため、「ストレスチェックもシステム化できる」と考えていました。
しかし、ストレスチェックを担当する別部門では、従来から利用している外部のストレスチェックサービスに満足しており、システム変更に対して消極的でした。結果として、以下のような状況が発生してしまいました
- 健康診断結果はシステムで管理
- ストレスチェックは従来通り外部サービスで実施
- ストレスチェック結果は後付けでシステムに投入
- 集団分析は外部サービスとシステムの両方で実施
二重運用による課題
運用面での課題
- 同じ従業員の健康情報が複数のシステム・サービスに分散
- データの分散による効率的な情報管理の阻害
- システム利用料と外部サービス利用料の両方が発生
- 担当者の業務負荷増大(複数システムでの作業が必要)
情報管理面での課題
- 複合データ(例:長時間労働データとストレスチェック)の関連分析が困難
- 産業医面談時の情報参照が非効率
- システム間でのデータ整合性確認の手間
部門間連携不足の根本原因
意思決定プロセスの問題
- システム導入の検討段階でストレスチェック担当部門が参画していない
- 各部門の業務要件や課題が十分に共有されていない
- 導入効果の評価基準が部門ごとに異なる
- システム化による影響範囲の認識が不十分
組織文化・慣習の問題
- 従来のやり方に対する愛着や安心感
- 新しいシステムに対する不安や抵抗感
- 部門間の縦割り意識による情報共有不足
- 変更に伴うリスクを避けたがる保守的な姿
対策:全社的な健康管理システム導入体制の構築
導入前の体制構築
- 健康管理に関わる全部門の代表者による検討委員会の設置
- 各部門の現状業務と課題の共有セッションの実施
- システム化による影響範囲の全社的な確認
- 統合運用による効果とリスクの事前評価
段階的な統合アプローチ
- まず健康診断結果管理のシステム化を完了
- ストレスチェック担当部門との協議を重ねて要件を整理
- 外部サービスとの比較検討を丁寧に実施
- 過去のストレスチェックデータをシステムに移行できるかの確認
- パイロット実施による検証を経て本格導入
まとめ
健康管理システムでのストレスチェック機能を成功させるためには、以下の要点を押さえることが重要です。
技術面での対策
- ITリテラシー格差に配慮したシステム選定と運用設計
- 紙・Web混在実施への適切な対応とコスト管理
- 職場環境改善を目的とした集団分析の活用
運用面での対策
- 分析結果の正しい解釈と参加型改善施策の実施
- 部門間連携による統合的なシステム運用
- 継続的な運用改善のためのPDCAサイクルの確立
体制面での対策
- 全関係部門の合意に基づく段階的な移行計画
- 専門家による継続的なサポート体制の構築
- 従業員の不安解消と協力獲得のための丁寧な説明
ストレスチェック機能のシステム化は、適切に実施すれば従業員の健康管理と職場環境改善の両方を効率的に推進できる優れた取り組みです。2028年の50人未満の事業所への義務化拡大を見据え、これらの落とし穴を事前に理解し、適切な対策を講じることで、システム導入を成功に導き、真の職場環境改善を実現していきましょう。
よくある質問
Q1: ストレスチェックのシステム化で受検率が下がった場合の対処法は?
システム化が原因かは慎重に検討をしなければなりませんが、ITリテラシーが原因の場合は、操作サポートの充実と段階的な移行が効果的です。システムの操作性改善をベンダーに要求し、受検率を維持することを目標に、必要に応じて一時的なハイブリッド実施も検討しましょう。
Q2: 従来の外部委託業者から自社システムに移行する際の注意点は?
過去のデータ形式と新システムでの互換性、従来の分析レポートと同等あるいは分析で求めたい内容がシステムで出力できるか、過去のストレスチェックデータをシステムに移行できるかを事前に確認することが重要です。また、これまで運用も外部委託していた場合は、自社システムでどのように運用するのか、あるいは運用は外部委託をするのかも検討が必要です。
Q3: 部門間でストレスチェックの運用方針が異なる場合はどうすれば良いですか?
健康管理に関わる全部門の代表者による検討委員会を設置し、各部門の要件と課題を共有することが重要です。統合運用による効果とコストを比較検討し、段階的な統合アプローチで部門間の合意を得ながら効率的なシステム運用を実現しましょう。
執筆・監修
WellaboSWP編集チーム
「機能する産業保健の提供」をコンセプトとして、健康管理、健康経営を一気通貫して支えてきたメディヴァ保健事業部産業保健チームの経験やノウハウをご紹介している。WellaboSWP編集チームは、主にコンサルタントと産業医・保健師などの専門職で構成されている。株式会社メディヴァの健康経営推進チームに参画している者も所属している。