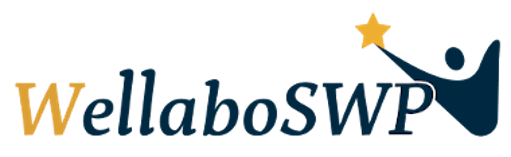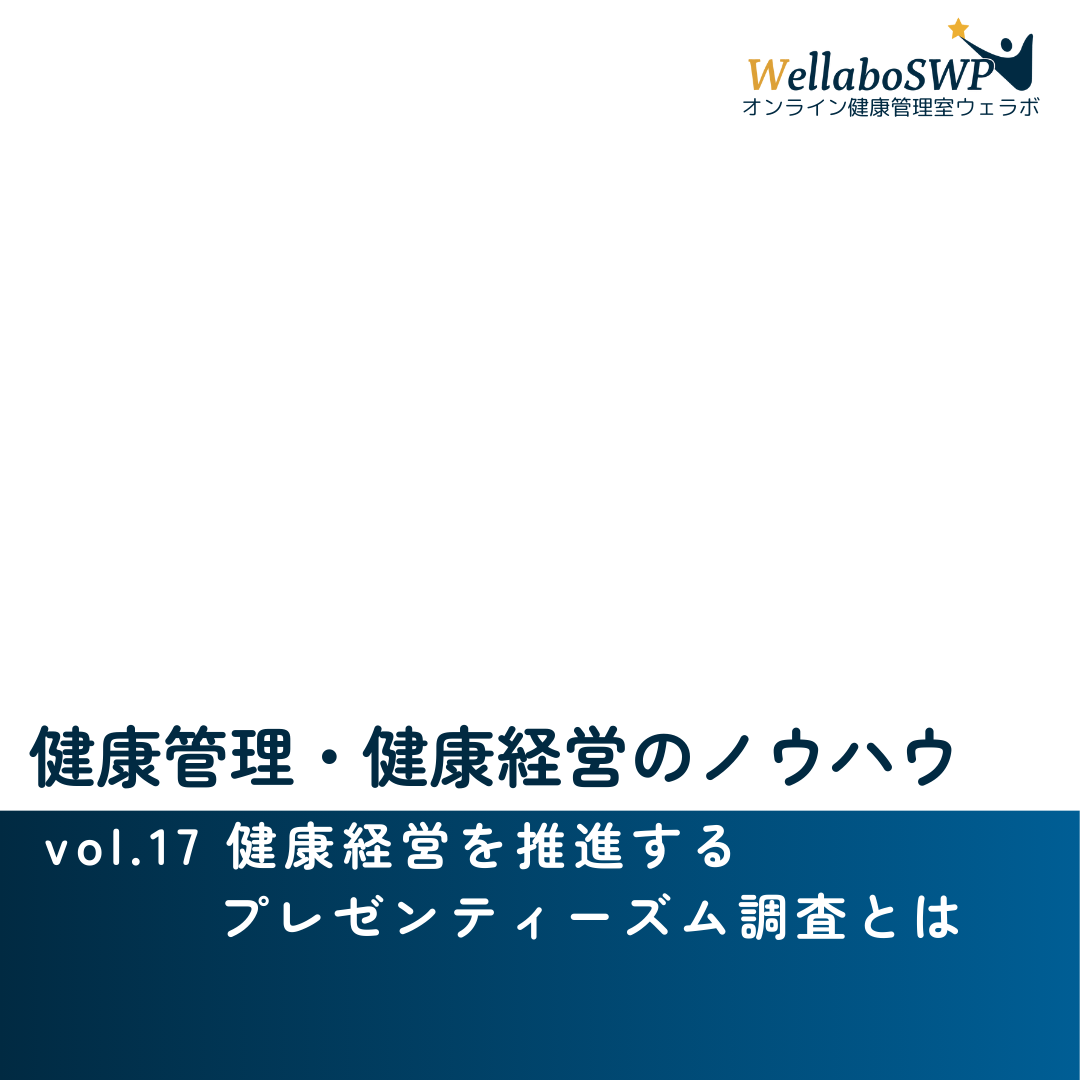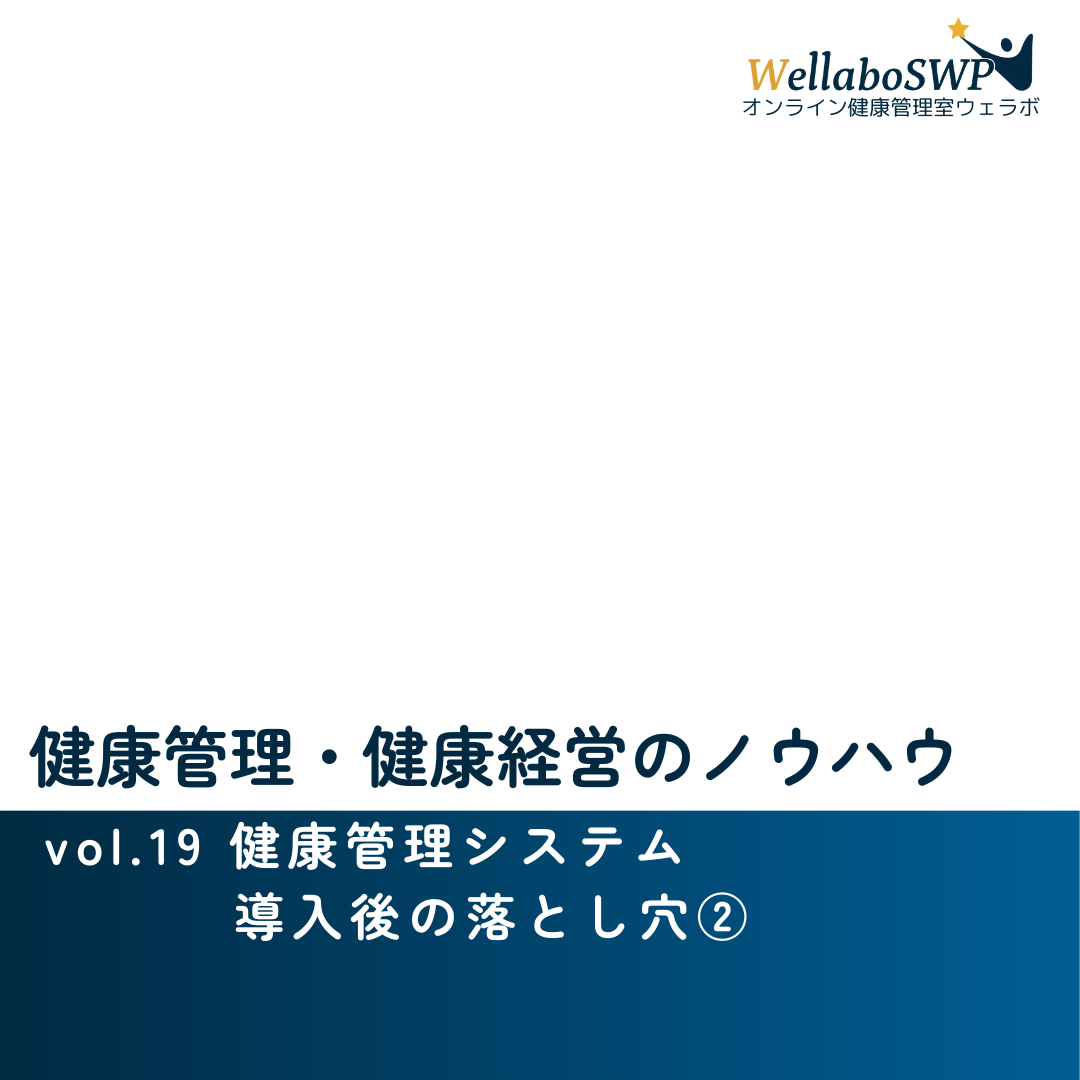健康管理システム導入後の落とし穴① 健康診断結果管理編
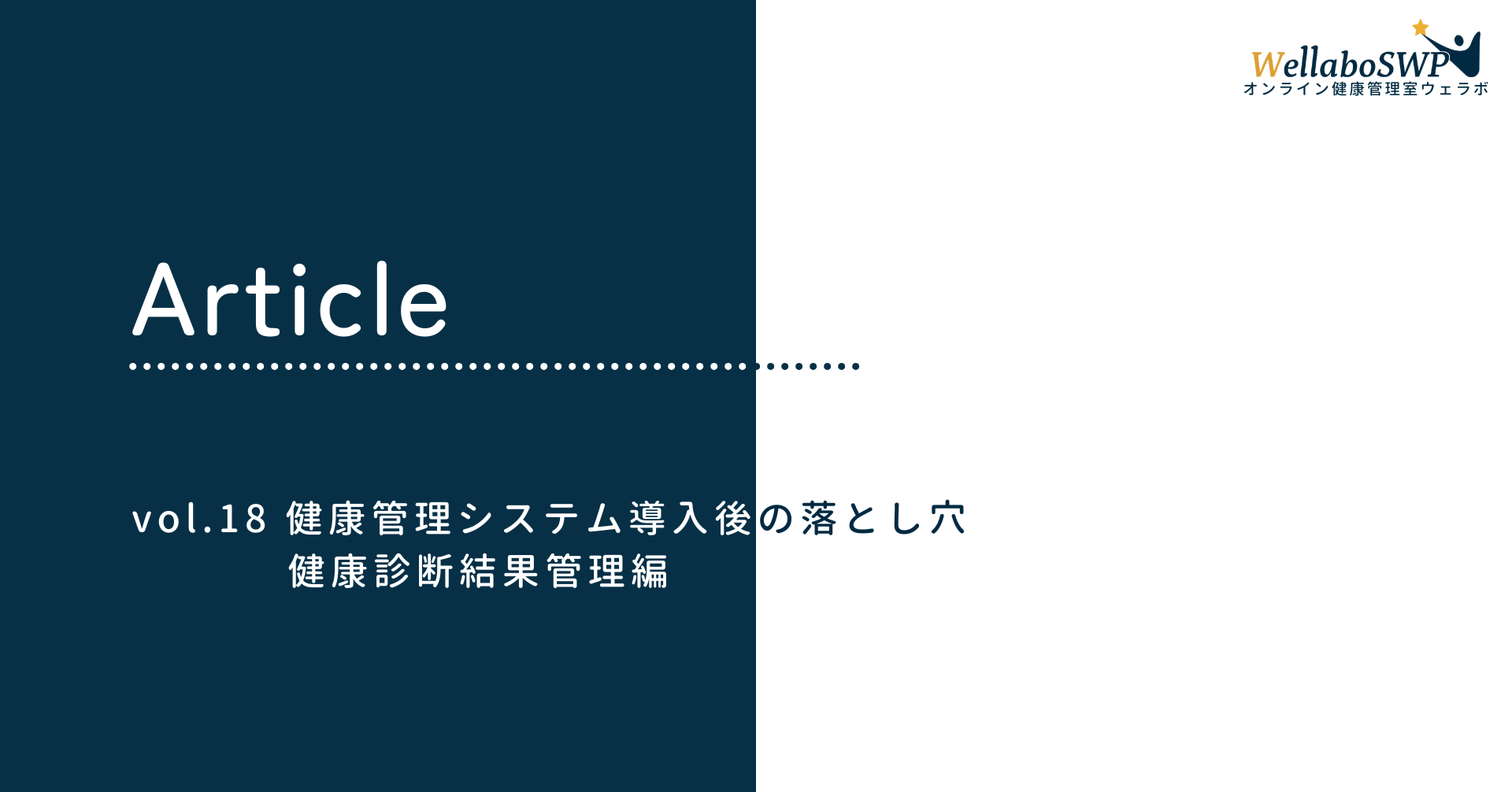
健康管理システムの導入を検討している、または既に導入したものの期待した効果を得られずに悩んでいる企業担当者の方へ。本シリーズでは、健康管理システムの設計者・開発者の視点から、導入後によくある問題とその解決策を解説します。
第1回は、健康管理システムで最もよく使われる機能である「健康診断結果管理」に焦点を当て、多くの企業が直面する現実的な課題をお伝えします。
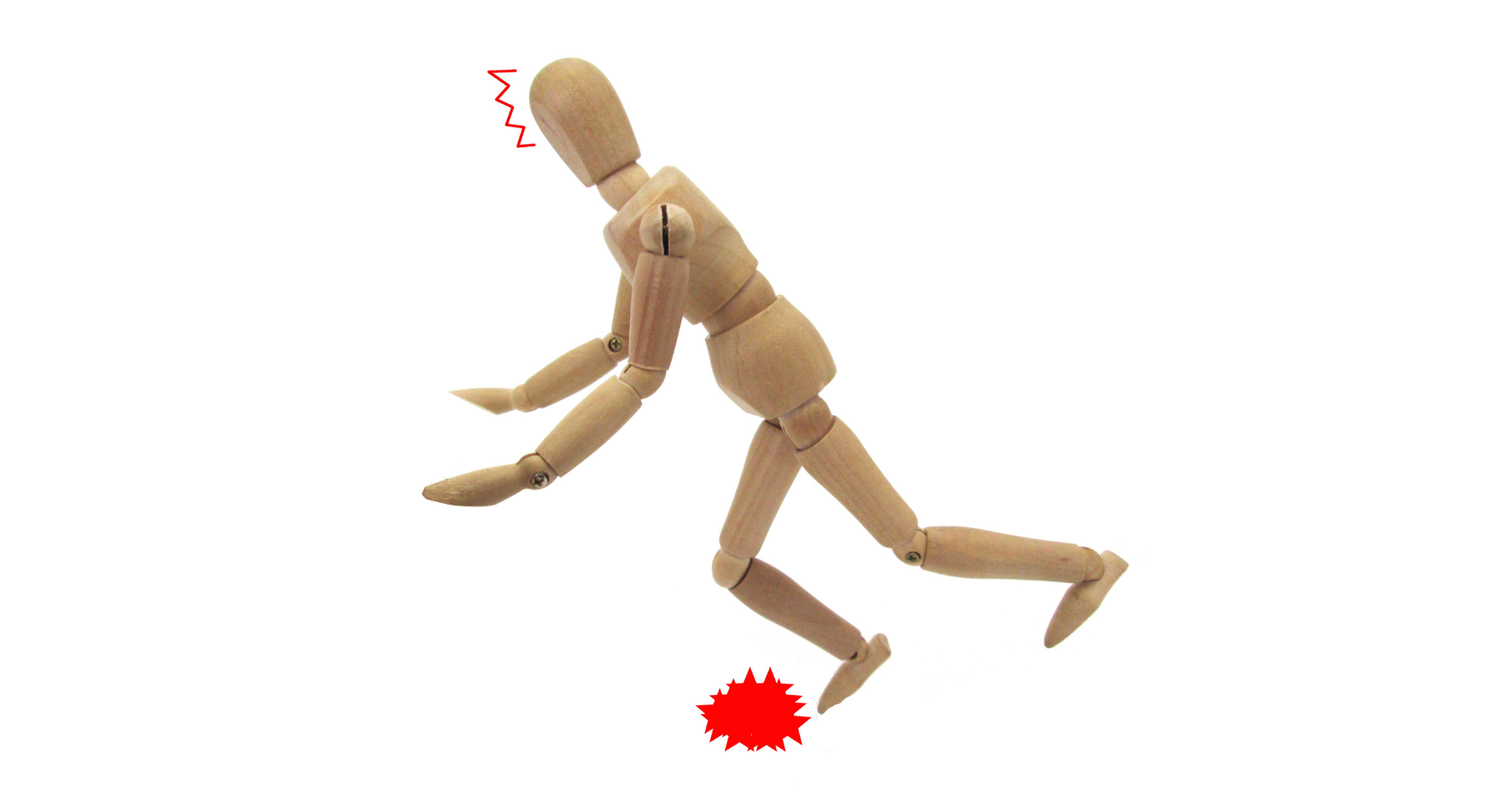
なぜ健康診断結果管理で問題が起きるのか
健康管理システムを導入する企業の多くが「健康診断結果をデジタル化して効率的に管理したい」という目的を持っています。しかし、この一見シンプルに思える機能こそが、実は最も多くの落とし穴を抱えているのが現実です。
健康診断結果管理が困難な理由は、健康管理システムが「理想的な業務フロー」を前提として設計されている一方で、企業の実際の運用は多種多様であることにあります。特に、健診機関との連携方法、データの取得・加工プロセス、産業医との業務分担など、企業ごとに大きく異なる部分でシステムと現実のギャップが生まれやすいのです。
落とし穴1:健診機関からのデータ取得問題
データ形式の統一困難
健康管理システムで健康診断結果を管理するためには、まず健診機関からデータ形式で結果を受け取る必要があります。しかし、ここで最初の大きな問題が発生します。
多くの企業は複数の健診機関を利用しています。本社は大手健診センターA社、工場がある地方拠点は地域の医師会健診センターB社といった具合です。さらに医療機関の選択を任意としている企業もあります。
問題は、これらの健診機関が提供するデータ形式がそれぞれ異なることです。A社はCSV形式、B社はExcel形式、C社は独自のシステムからPDF出力のみ、という状況は珍しくありません。さらに、同じCSV形式であっても、項目の並び順、項目名、データの表記方法(数値の単位、正常/異常の表記など)が健診機関ごとに異なります。
データ化の追加コストと時間
もし健診機関がデータでの納品に対応していない場合、または追加料金が発生する場合は、紙の健診結果をデータ化する作業が必要になります。この作業は想像以上に時間とコストがかかります。
内製でデータ化を行う場合の問題:
- 大量の個人情報を手作業で入力する精神的負担
- 入力ミスのリスクと確認作業の工数
- 担当者の本来業務を圧迫する時間的負担
外注でデータ化を行う場合の問題:
- 想定外の高額なコスト発生
- データ化完了まで2〜3ヶ月の長い納期
- 個人情報を外部に委託することのセキュリティリスク
法的期限との競合
労働安全衛生法では、健康診断実施後3ヶ月以内に就業に関する医師の意見を聴取することが義務付けられています。しかし、データ化や変換作業に時間がかかりすぎると、この法定期限に間に合わなくなるリスクがあります。
結果として、「システムへの登録は後回しにして、とりあえず紙やExcelで産業医判定を進める」という事態が発生し、システム導入の意味が失われてしまいます。
落とし穴2:産業医のシステム習熟問題
デジタルツール慣れの個人差
産業医の中には、長年の経験でExcelや紙での判定業務に慣れ親しんでいる方も多くいらっしゃいます。新しいシステムの操作方法を覚えることは、年齢や個人的なITスキルによって大きく負担が異なります。
特に嘱託産業医の場合、複数の企業を担当しているため、企業ごとに異なる健康管理システムの操作方法を覚えることは現実的ではありません。「このシステムは使いづらいので、今まで通りExcelで判定結果をもらいたい」という要望が出されることも少なくありません。
システム判定機能の活用格差
健康管理システムには「一括判定機能」が搭載されていることがあります。これは、事前に設定された判定基準に基づいて、複数の健康診断結果を就業区分を判定する機能です。判定結果については産業医が確認する必要がありますが、適切に活用すれば、産業医の判定業務を大幅に効率化し、判定の一貫性も保てる優れた機能です。
しかし、システムにこの機能がない場合や機能を使いこなせない産業医の場合、一件一件手作業で判定を行うことになり、従来のExcel判定よりも時間がかかってしまうこともあります。システムの画面を開いて、判定対象者を選択し、判定内容を入力して保存する、という一連の操作を健診受診者全員分繰り返す行為がどの程度効率的にできるのかは確認しておく必要があります。システムによっては産業医の確認しやすい仕様になっておらず、産業医が強く負担感を感じることもあります。
専門職の協力体制構築の難しさ
産業医、とくに嘱託産業医の場合は、企業の従業員ではなく外部の専門家として関わることが多いため、システム導入プロジェクトへの参画意識が低くなりがちです。
「システムの都合に合わせて業務を変えるつもりはない」「今までの方法で問題なくやってきたのに、なぜ変える必要があるのか」といった反応を示されることもあります。このような状況では、システム導入の効果を最大化することは困難になります。
落とし穴3:既存の業務フロー活用不可問題
健診機関での判定完了済みデータの扱い
一部の企業では、健診機関に産業医が所属しており、健康診断の実施と同時に就業判定まで完了した状態で結果が提供されています。この運用方法は、企業側の負担軽減という点で非常に有効です。
しかし、多くの健康管理システムは「企業内で産業医判定を行う」ことを前提として設計されています。そのため、既に判定が完了している健診結果を「判定済み」としてシステムに取り込む機能がない場合があります。
この場合、健診機関での判定とは別に、システム上で再度産業医判定を実施する必要が生じ、二重作業となってしまいます。産業医にとっても、「既に判定した内容をなぜもう一度システムで判定しなければならないのか」という疑問が生まれ、システム活用への抵抗感につながります。
判定根拠の可視化不足
健診機関で就業判定が完了している場合でも、さらにその結果をシステムに取り込むことができたとしても、「何の項目がどのような理由で引っかかったのか」という詳細な判定根拠がシステム上で確認できないことがあります。
これにより、保健師や健康管理担当者が受診勧奨や保健指導を行う際に、「なぜこの判定になったのか分からない」という状況が発生し、適切なフォローができなくなってしまいます。結果として、保健師や担当者が改めて健診結果を一つ一つ確認し直すという追加作業が発生します。
落とし穴4:受診勧奨業務の非効率化
全件確認の必要性
システムに健康診断結果を登録したとしても、受診勧奨が必要な対象者を効率的に抽出できない場合があります。特に、以下のような課題が発生しがちです
判定結果の詳細確認作業:
システム上で「要受診勧奨」と表示されていても、具体的にどの項目で引っかかったのか、どの程度の緊急性があるのかが一目で分からず、保健師や担当者が個別に確認する必要がある
優先順位付けの困難:
受診勧奨対象者が多数いる場合、どの従業員から優先的にアプローチすべきかを判断するための情報がシステム上で整理されていない
受診勧奨の実施状況管理
受診勧奨を実施した後の管理も重要な問題です。「いつ、誰に、どのような内容で受診勧奨を行ったか」「その後の受診状況はどうか」「再検査の結果はどうだったか」といった一連の流れをシステム上で管理できない場合、結局Excel等での並行管理が必要になってしまいます。
健康診断結果管理を成功させるための対策
導入前の準備段階での対策
現状業務フローの詳細分析: 健診機関から結果受領、データ変換、産業医判定、受診勧奨、フォローまでの一連の流れを詳細に可視化し、関係者全員で共有する
健診機関との事前調整:
- 各健診機関のデータ提供形式と追加料金を詳細確認
- データ提供までの期間を契約前に明確化
- システムが求める形式との適合性を事前評価
産業医との合意形成:
- システム導入の目的と期待効果を丁寧に説明
- 産業医の既存業務フローを尊重した導入計画の策定
- システムデモンストレーションによる事前体験の実施
システム選定段階での対策
柔軟なデータ取込み機能の確認:
- 複数の健診機関データ形式に対応可能か
- データ変換機能やカスタマイズ可能性はあるか
- 判定済みデータの取込み機能があるか
業務フロー適合性の評価:
- 自社の現状業務フローでそのまま使えるか
- 必要な業務フロー変更は現実的に実行可能か
- カスタマイズや設定変更で対応可能な範囲はどこまでか
一括処理機能の充実度:
- 一括判定機能の精度と使いやすさ
- 受診勧奨対象者の効率的な抽出機能
導入・運用段階での対策
事前のデモンストレーション活用:
導入前に必ずでも環境を使ったデモンストレーションを実施し、システムの操作性や自社の業務フローとの適合性を事前に確認する
十分な研修期間の設定:
産業医、保健師、事務担当者それぞれに適した研修プログラムを準備し、全員がシステムを使いこなせるまで十分な期間を確保する
データ管理体制の構築
データ品質管理の仕組み:
- 健診機関からのデータ受領時のチェック項目を明確化
- データ変換時のエラー検出と修正手順の標準化
- システム登録後のデータ整合性確認プロセスの確立
クラウドサービス活用のメリット:
クラウド型システムの場合、バックアップやシステム障害対応はサービス提供者側で実施されるため、企業側は業務継続プランの策定に集中できる
産業医との協力体制構築のポイント
システム導入の必然性を共有
産業医にシステム活用の協力を求める際は、単に「新しいシステムを導入したので使ってください」ではなく、なぜシステムが必要なのか、どのような効果が期待できるのかを具体的に説明することが重要です。
効果的な説明内容:
- 従業員数増加に伴う判定業務の効率化の必要性
- データの一元管理による判定精度の向上
- 経年変化の把握による的確な健康指導の実現
- 法的要件への確実な対応
産業医の業務スタイルに配慮した設定
システムの設定や運用ルールを決める際は、産業医の既存の業務スタイルを最大限尊重することが成功の鍵です。
配慮すべきポイント:
- 判定作業の時間帯や頻度の希望
- 既存の判定基準やフローとの整合性
- システム操作の簡便性に対する要求レベル
継続的なサポート体制
システム導入後も、産業医が困った時にすぐに相談できる体制を整備することが重要です。操作方法の質問、システムの不具合報告、業務フローの改善提案などに迅速に対応できる窓口を明確にしておきましょう。
健診機関との連携体制見直し
契約条件の再交渉
既存の健診機関との契約を見直し、システム連携を前提とした条件に変更することを検討しましょう。
交渉ポイント:
- データ提供形式の統一化
- データ提供の追加料金の削減または無料化
- データ提供までの期間短縮
- システム取込みに適したデータ形式での提供
健診機関の集約検討
複数の健診機関を利用している場合は、システム連携の観点から健診機関の集約を検討することも有効です。ただし、地域性や受診者の利便性とのバランスを慎重に考慮する必要があります。
よくある質問への対応
Q1: 健診機関を変更せずにシステム活用する方法はありますか?
健診機関を変更できない場合でも、以下の方法でシステム活用は可能です:
- システムベンダーに現在のデータ形式での取込み対応を依頼
- データ変換ツールの活用による自動変換の仕組み構築
- 段階的なデータ化計画による業務負荷の分散
Q2: 産業医がシステムを使ってくれない場合はどうすれば良いですか?
産業医の協力を得るための段階的アプローチを推奨します:
- まずは閲覧機能のみから開始し、システムに慣れてもらう
- Excel出力機能を活用して、従来の業務スタイルとシステムを併用
- システム操作の研修や個別サポートを丁寧に実施
- システム活用のメリットを具体的な数値で示す
Q3: システム導入後に業務負荷が増えてしまった場合の対処法は?
業務負荷増加の原因を特定し、段階的に改善していくことが重要です:
- 負荷増加の具体的な原因分析(データ変換、操作習熟、業務フロー変更など)
- 原因に応じた対策の優先順位付け
- システムベンダーへの改善要望やカスタマイズ検討
- 必要に応じて外部サポートの活用
まとめ:健康診断結果管理成功の要点
健康管理システムの健康診断結果管理機能を成功させるためには、以下の要点を押さえることが重要です
事前準備の徹底:
現状業務フローの詳細分析と関係者との合意形成
現実的な導入計画:
完璧を求めず、事前のデモンストレーションと十分な研修期間を確保した導入計画
継続的な改善体制:
導入後の課題を迅速に解決できるサポート体制の構築
効果測定の実施:
具体的な指標による定期的な効果測定と改善
健康診断結果管理は健康管理システムの中核機能でありながら、最も多くの落とし穴が潜んでいる領域でもあります。これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることで、システム導入を成功に導き、真の業務効率化と健康経営の推進を実現することができるでしょう。
執筆・監修
WellaboSWP編集チーム
「機能する産業保健の提供」をコンセプトとして、健康管理、健康経営を一気通貫して支えてきたメディヴァ保健事業部産業保健チームの経験やノウハウをご紹介している。WellaboSWP編集チームは、主にコンサルタントと産業医・保健師などの専門職で構成されている。株式会社メディヴァの健康経営推進チームに参画している者も所属している。