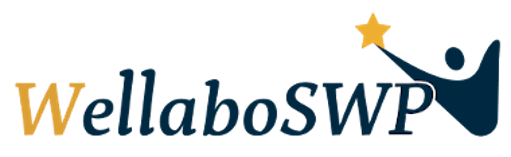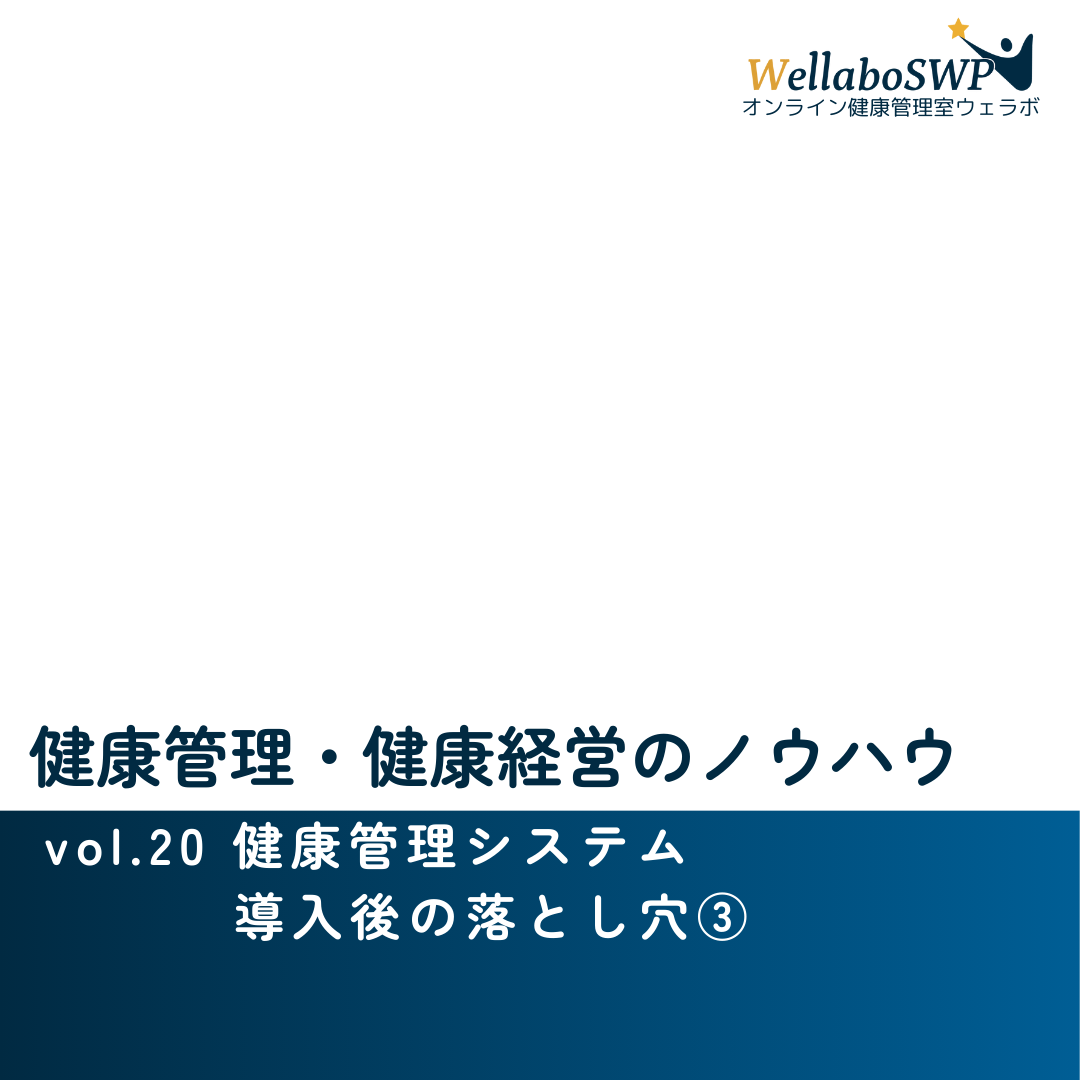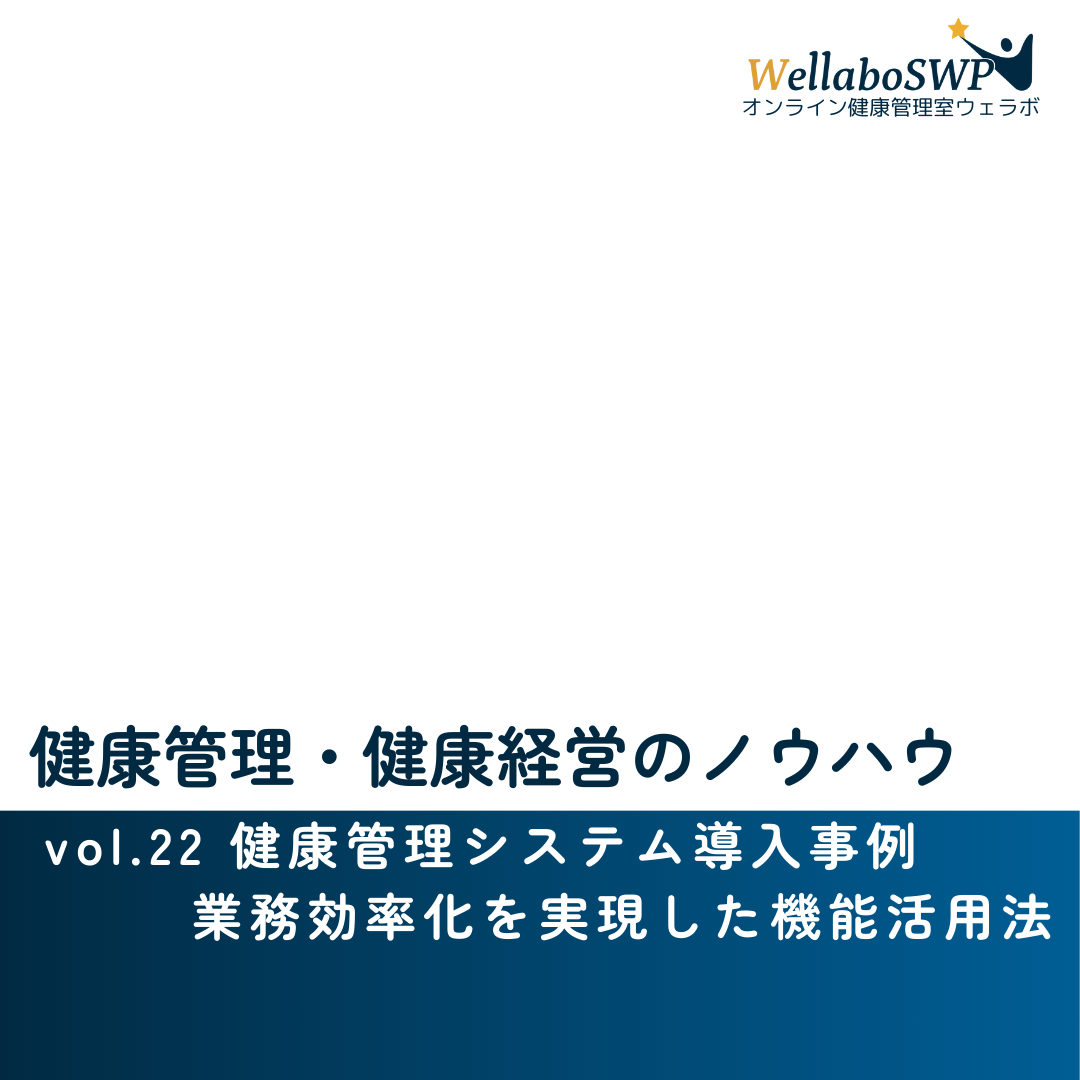健康管理システム導入後の落とし穴④ 長時間労働管理機能編
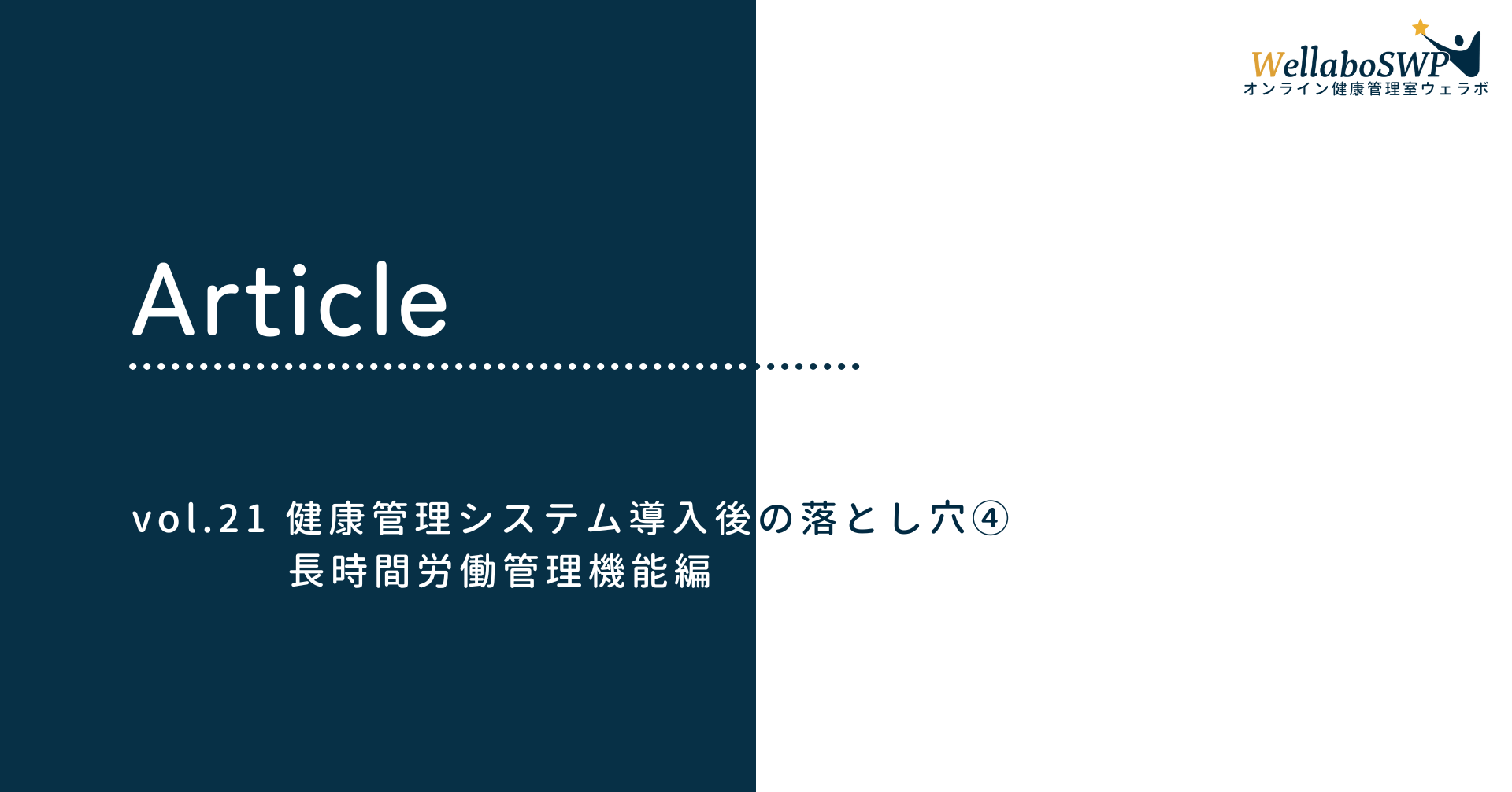
健康管理システムの導入を検討している、または既に導入したものの期待した効果を得られずに悩んでいる企業担当者の方へ。本シリーズでは、健康管理システムの設計者・開発者の視点から、導入後によくある問題とその解決策を解説しています。
第4回は、働き方改革関連法の施行により重要性が高まっている「長時間労働管理機能」に焦点を当てます。法令遵守のためにシステムを導入したものの、実際の運用では「結局Excelでの管理が必要」「企業独自の基準に対応できない」といった問題に直面する企業が少なくありません。今回は、長時間労働管理機能で発生する3つの典型的な落とし穴と、その対策について詳しく解説します。
なぜ長時間労働管理機能で問題が起きるのか
長時間労働管理は、2019年の働き方改革関連法施行により、多くの企業にとって重要な法的義務となりました。時間外労働の上限規制(単月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以下)への対応や、長時間労働者に対する医師の面接指導の実施など、企業が対応すべき事項は多岐にわたります。
しかし、健康管理システムの長時間労働管理機能は、「法定基準への最低限の対応」を前提として設計されているものもあります。一方で、実際の運用では「法定基準よりも厳しい自社基準を設けたい」「独自の疲労度チェックを実施したい」「面談の意思確認から実施まで一元管理したい」といったニーズを持つ企業があります。
このギャップにより、システムを導入したものの「思っていた運用ができない」「結局手作業での管理が必要」という状況に陥る企業が後を絶ちません。

落とし穴1:基準設定の柔軟性不足による形骸化
企業独自基準への対応不可
企業によっては、法定基準(単月100時間、2〜6ヶ月平均80時間)よりも厳しい独自基準を設けて、より早期の段階で長時間労働者への対応を行いたいと考えています。例えば、月45時間や60時間の段階で疲労度確認を実施し、必要に応じて産業医面談を実施するという運用です。
典型的な問題のケース
A社では、健康経営の一環として月45時間の残業を超えた従業員に対して疲労度チェックを実施し、必要に応じて産業医面談を実施する運用を行っていました。健康管理システム導入時、長時間労働管理機能があることを確認して導入を決めましたが、実際に使用してみると以下の問題が発生しました
- システムの基準設定は法定基準(100時間、80時間)のみ対応
- 月45時間での対象者抽出機能がない
- 2〜6ヶ月平均の自動計算が80時間基準のみで、独自基準での計算ができない
- 結果として、勤怠データをシステムからExcelにエクスポートし、手動で45時間超過者を抽出する作業が必要
2〜6ヶ月平均の自動算出機能不足
法定基準では「2〜6ヶ月平均80時間以下」という規定がありますが、この平均値を自動で算出できないシステムが存在します。また、企業独自基準(例:2〜6ヶ月平均60時間)での自動算出に対応していない場合もあります。
具体的な問題例
B社では、法定基準だけでなく企業独自の基準として「2〜6ヶ月平均60時間」で早期アラートを出したいと考えていました。しかし、導入したシステムでは以下の問題が発生しました
- 2〜6ヶ月平均の自動算出機能はあるが、80時間基準のみ
- 企業独自で行いたい基準(例:60時間)での平均算出ができない
- 結果として、月次で勤怠データをExcelにエクスポートし、手動で平均値を計算する作業が継続
対策のポイント
- システム選定時に企業独自基準設定の可否と設定方法の事前検証
- 2〜6ヶ月平均算出機能の対応基準値の確認
- 必要に応じてカスタマイズ対応の可否と費用の確認
落とし穴2:疲労度確認機能の不足による運用の分断
システム化できない疲労度チェック
長時間労働者への対応では、単に労働時間を把握するだけでなく、実際の疲労度や体調を確認することが重要です。厚生労働省が公開している「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」などを活用している企業もありますが、健康管理システムには疲労度確認機能が搭載されていないことがあります。あるいは、搭載されていても使いづらい、質問項目が固定で変更できないといった問題があります。
典型的な問題のケース
C社では、月80時間を超える長時間労働者に対して、以下のような運用を行っていました
- 勤怠システムから月80時間超過者を抽出
- 対象者に厚生労働省の疲労蓄積度自己診断チェックリストを配布
- 回答結果をもとに産業医面談の要否を判定
- 面談希望者に対して日程調整を実施
健康管理システム導入後、勤怠データの取り込みまではできるようになりましたが、疲労度チェック機能がないため、以下の問題が発生しました
- 80時間超過者の抽出はシステムでできるが、疲労度チェックは別途Excelで管理
- チェック結果の集計・分析が手作業
- 面談希望の意思確認もシステム外での管理が必要
- 結果として、システム導入前と業務負荷がほとんど変わらない状況
面談希望確認と日程調整の非効率
長時間労働者への産業医面談は、法的には「医師による面接指導の申出があった場合」に実施義務が生じます。そのため、まず対象者に面談希望の有無を確認し、希望者に対して日程調整を行う必要があります。
この一連のプロセスをシステム化できれば大幅な効率化が期待できますが、システムによっては以下の機能が不足している場合があります
不足している機能例
- 対象者への自動通知機能
- Web上での面談希望有無の回答機能
- 面談実施後の記録管理機能
対策のポイント
- 現在の疲労度確認方法の詳細分析とシステム化要件の明確化
- 疲労度チェック機能の有無と利用可能なチェックリストの確認
- 段階的なシステム化による運用の改善
落とし穴3:運用フローの分断による二重管理の発生
一気通貫での管理ができない現実
理想的な長時間労働管理は、「勤怠データ取得→基準超過者抽出→疲労度確認→面談実施→事後フォロー」という一連の流れがシステム内で完結することです。しかし、実際には各段階でシステムの機能不足により、外部ツールでの作業が必要になることが多くあります。
典型的な分断パターン
D社の場合
- 勤怠データ取得:勤怠システムから健康管理システムへデータ連携(○)
- 基準超過者抽出:月45時間基準での抽出ができないため、Excelで手動抽出(×)
- 疲労度確認:システムに機能がないため、メール+Excel管理(×)
- 面談実施:面談記録はシステムに入力(○)
- 事後フォロー:フォロー管理機能がないため、Excel管理(×)
この結果、健康管理システムは「勤怠データの保管場所」と「面談記録の保管場所」としてしか機能せず、実際の業務効率化にはつながりませんでした。
データの整合性確保の困難
システムとExcelでの並行管理が発生すると、データの整合性を保つことが困難になります。特に以下のような問題が発生しがちです
データ整合性の問題例
- システムの勤怠データとExcel管理の対象者リストの不一致
- 疲労度確認の実施状況がシステムで把握できない
- 面談実施状況とフォロー状況の関連が見えない
- 月次・年次での実績集計が困難
E社では、長時間労働管理の実績を経営層に報告する際、システムとExcelの両方からデータを収集して手動で突合作業を行う必要があり、担当者の大きな負担となっていました。
法的要件への対応漏れリスク
運用が分断されることで、法的要件への対応漏れが発生するリスクも高まります。
対応漏れのリスク例
- 面接指導の申出があったにも関わらず、日程調整が漏れる
- 面接指導実施後の就業上の措置が記録されない
- 長時間労働の改善策が実施されたかフォローできない
- 労働基準監督署への報告で必要な情報が不足する
対策のポイント
- 現在の運用フロー全体をマッピングし、システム化可能な範囲を明確化
- 一気通貫でのシステム化が困難な場合の段階的改善計画の策定
- システム間連携やAPI活用による作業自動化の検討
- 運用マニュアルの整備による人為的ミスの防止
まとめ:長時間労働管理機能成功の要点
健康管理システムの長時間労働管理機能を成功させるためには、以下の要点を押さえることが重要です
事前準備の徹底
自社の36協定内容、独自基準、現在の運用フローの詳細分析
現実的な導入計画
一気通貫でのシステム化にこだわらず、段階的な改善計画の策定
法的要件の確実な対応
最低限の法的要件は確実に満たせるシステム選択
継続的な改善体制
運用開始後の課題を迅速に解決できるサポート体制の構築
長時間労働管理は、法的義務への対応と従業員の健康保護という両方の観点から重要な機能です。しかし、システムの機能制約により期待した効果を得られないケースも多く見られます。これらの落とし穴を事前に理解し、自社の運用実態に合ったシステム選択と段階的な改善を行うことで、真の業務効率化と法的要件への確実な対応を実現することができるでしょう。
執筆・監修
WellaboSWP編集チーム
「機能する産業保健の提供」をコンセプトとして、健康管理、健康経営を一気通貫して支えてきたメディヴァ保健事業部産業保健チームの経験やノウハウをご紹介している。WellaboSWP編集チームは、主にコンサルタントと産業医・保健師などの専門職で構成されている。株式会社メディヴァの健康経営推進チームに参画している者も所属している。