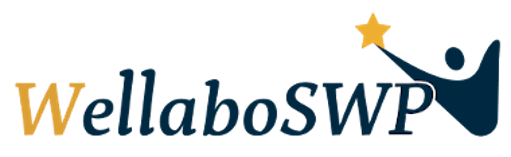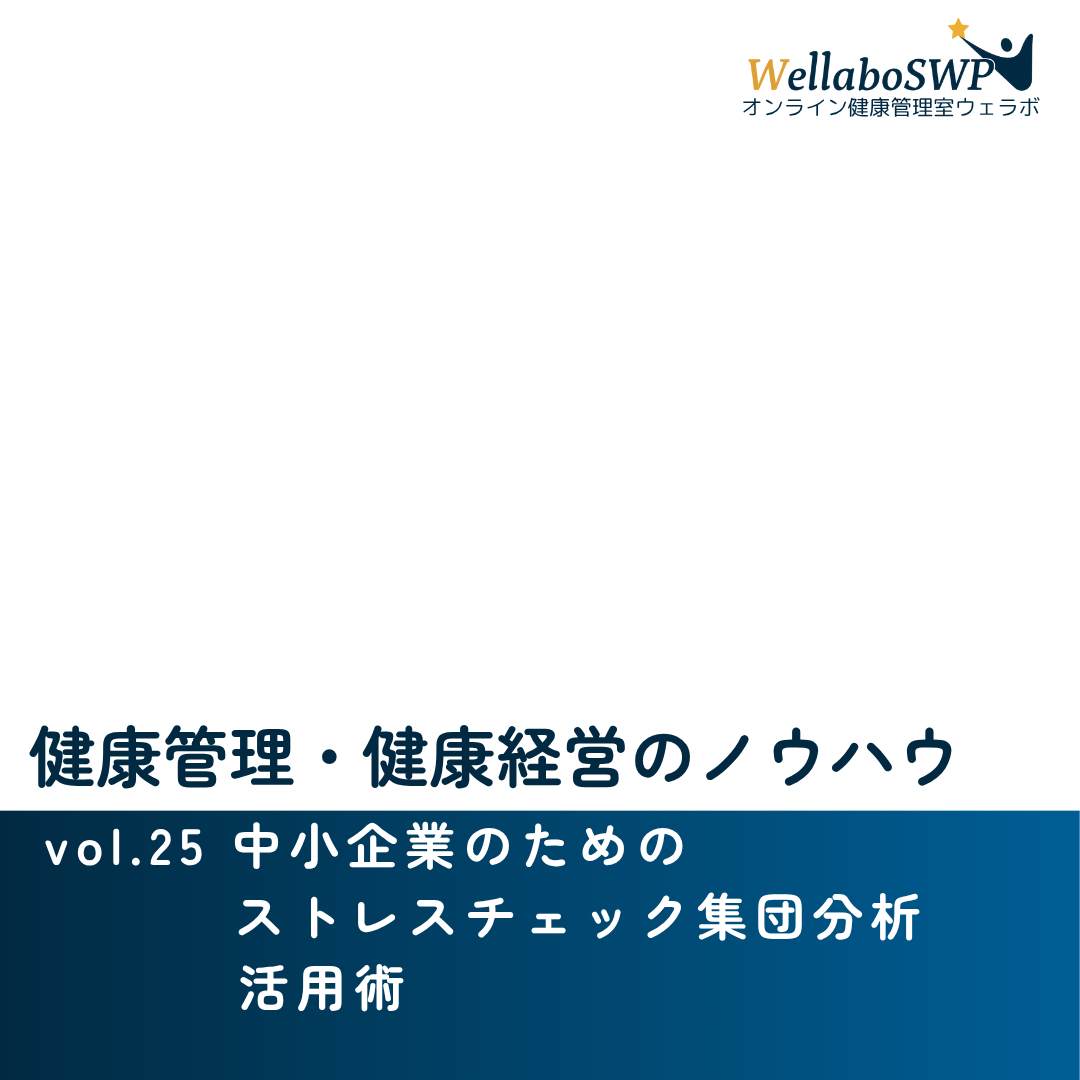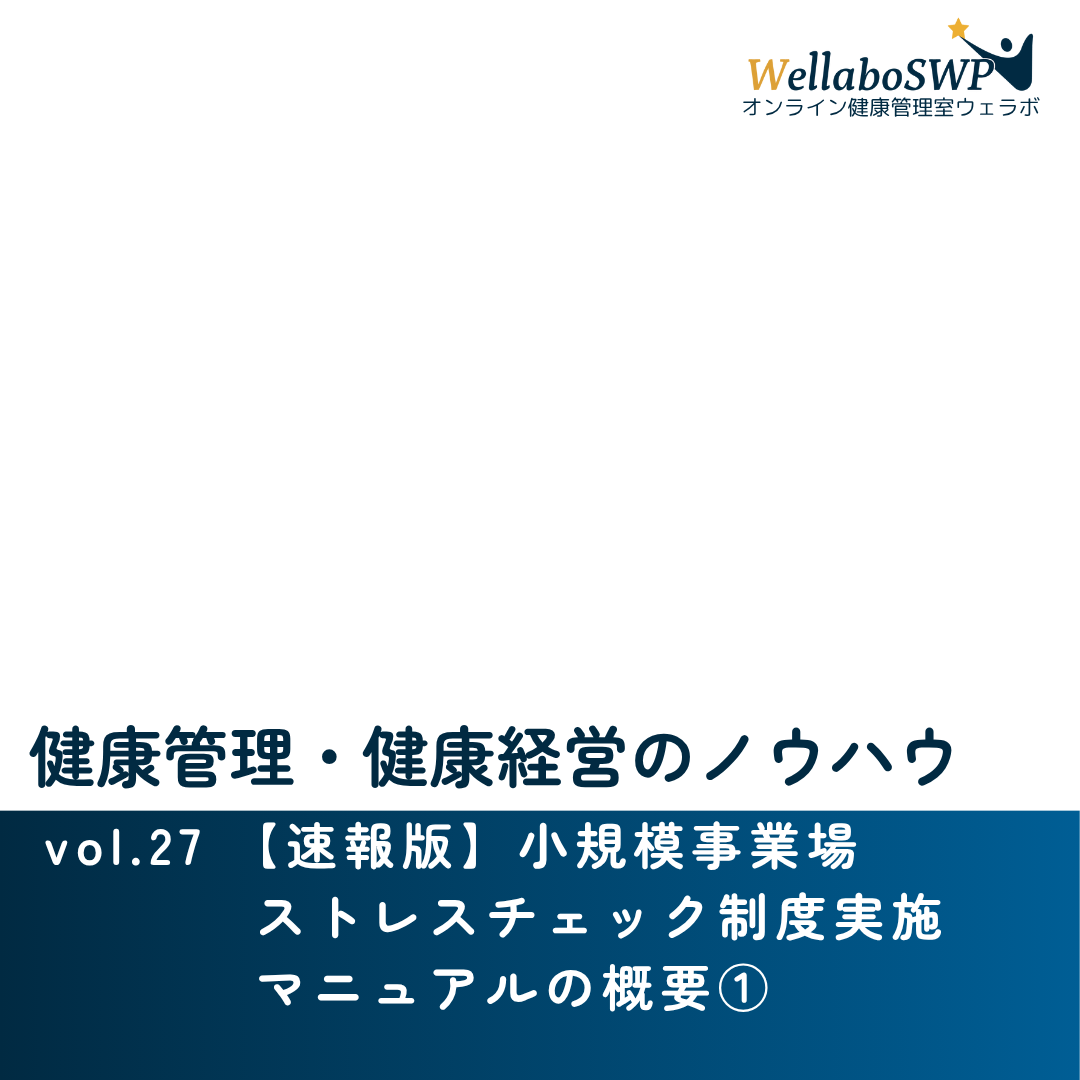令和7年度健康経営度調査を振り返る

2025年10月10日に令和7年度の健康経営度調査票の提出が締め切られました。今年度の調査票は例年と比較して変更点も多く、また変更点への対応の難易度も高かったことから、大規模法人部門の担当者はようやくその対応から解放され、ようやく一息つくことができたのではないでしょうか。とはいえ、来年度に向けて予算採りも含めて来年度の準備をしていかなければいけない時期に差し掛かっています。今年度の調査票にはまだまだ十分には対応できなかったという担当者様はこれからその対応も検討していかなければなりません。
本記事では、今年度の健康経営度調査における弊社コンサルタントの支援経験から、問い合わせの多かった設問とその対応、調査票における感想と課題感をまとめました。
健康経営度調査票の主な変更点についてはこちら

最も相談の多かった設問:Q17「健康経営の推進方針・目標・KGI設定」
経営上の課題に対する健康経営の戦略を問うQ17は、健康経営ガイドブック改訂版の影響を受けて大幅に変更されたこともあり、最も多くご相談を受けた設問となりました。特にKGIの具体的な設定方法、既存戦略からの解釈、新戦略マップの作成、KPI・KGIとの関連付け、推進方針・目標・KGIの一貫性のイメージ構築、KGI設定の社内承認プロセスなどが主な課題でした。
よくある困りごと
- 「KGIって何を設定すればいいの?」
- 「既存の取り組みから新しい戦略マップにどう転換する?」
- 「役員会承認が必要なレベルの変更になってしまう」
解決のポイント
経営方針と健康経営方針を連動させることが重要です。我々コンサルタントも顧客企業の経営方針や健康経営宣言を読み込み、例えば、「従業員の生産性向上」という経営目標に対して、「プレゼンティーイズム改善率○%」というKGIを設定するなど、具体的な数値目標への落とし込みを支援しました。また、戦略マップはガイドライン通りに改訂対応する必要があるのかという質問も多数いただきましたが、決してガイドライン通りに作成することが必須ではなく、自社の現状に合わせて達成可能な点から取り組んでいくことをお勧めしています。
情報開示における相談:Q18「健康経営の推進に関する社外開示」
各種指標の開示方法について、「何を開示すればいいかわからない」「HPでの見せ方がイメージできない」という声が多く寄せられました。
よくある困りごと
- 「各設問に該当する指標が思い当たらない」
- 「情報開示って具体的にどうすればいいの?」
- 「他社はどんな風に公開してるの?」
解決のポイント
弊社では、各設問に対応する指標を明確に提示し、実際のHP公開用のイメージ図と文章まで作成してご提案しました。また、他社の優良事例を共有することで、具体的なイメージを持っていただけるよう支援しました。情報開示は健康経営の透明性を高める重要な要素ですので、自社の取り組みを積極的にアピールする良い機会として捉えることが大切です。
コンサルタントが感じた今年度の変化
ポジティブな変化
1. 経営層の本気度が問われるように
形式的な「会議を何回やったか」から、「何を議論し、何を決めたか」という実質的な内容を問う設問に変わりました。これにより、本当に経営層が健康経営にコミットしているかが明確になります。
2. 戦略の一貫性が見えやすく
設問間の連動により、健康投資→プロセス評価→KGI→企業理念という流れが明確になりました。調査票に回答しながら、自社の健康経営の全体像を整理できるようになったのは大きな進歩です。
課題と感じた点
1. 施策の負担感が増大
「実施しているか」だけでなく、「どんな効果があったか」「どれだけ社員が参加したか」まで問われるようになり、正直なところ負担は増えました。特に中小規模の企業や、健康経営の専任担当者がいない企業にとっては、かなりハードルが高くなったと感じています。
2. 業種による不公平感く
柔軟な働き方や両立支援が重視されるようになりましたが、医療・介護・製造業など、現場での勤務が必須の業種では対応が困難な項目もあります。業種特性への配慮がもう少しあってもよいのではないでしょうか。
3. デジタルツール推奨の流れく
心の健康に関するデジタルツール利用の設問が追加されるなど、デジタル化推進の意図を感じました。しかし、すべての企業がすぐにデジタルツールを導入できるわけではありません。アナログな方法でも効果的な取り組みは評価されるべきだと思います。
健康経営度調査の課題 ~現場からの声~
今年度の支援を通じて、調査制度自体にもいくつかの課題が見えてきました。これらは批判ではなく、より良い健康経営の推進のための建設的な提案として受け止めていただければ幸いです。
企業規模・業種による公平性の問題
多くのコンサルタントから「資金面にゆとりがある会社が高ポイントになる印象」「体力があり余裕がある超大企業しかやれないような項目がある」という声が上がりました。特に、医療・介護・製造業など、現場での勤務が必須の業種では、柔軟な働き方や両立支援の実現に限界があります。
健康経営は本来、企業規模や業種を問わず、すべての企業が取り組むべきものです。中小企業や特定業種でも実現可能な評価軸の設定や、業種特性を考慮した評価方法の検討が必要ではないでしょうか。
新指標導入への懸念 ~POS、PSS、WSCをどう扱うか~
Q72で新たに導入されたPOS(Perceived Organizational Support:知覚された組織的支援)、PSS(Perceived Supervisor Support:知覚された管理職支援)、WSC(Workplace Social Capital:職場のソーシャルキャピタル)といった指標。確かに、POSが高まることで従業員が仕事にやりがいを感じ、組織へのコミットやパフォーマンス向上につながることは学術的に示されています。また、PSSによって上司から支えられていると感じることが組織全体への信頼につながることも理解できます。
しかし、これらの概念を実務でどう測定し、どう改善につなげるかについて、十分な情報提供がなされているとは言えません。例えば、職場のソーシャルキャピタルを測定する職業性簡易版ソーシャルキャピタル尺度があることは知られていても、その結果をどう解釈し、具体的にどんなアクションを取ればWSCが向上するのか、実務担当者が迷うケースが多いのです。
「健康経営を科学する」という方向性は素晴らしいのですが、新しい指標を次々と導入することが、かえって企業をミスリードし、本質的でない対応に追われる結果になることを懸念しています。これらの指標を真に活用するためには、測定方法だけでなく、改善事例や具体的な施策との紐付けまで含めた、実践的なガイダンスが不可欠です。
企業の独自性が失われる懸念
「フレームワークに当てはめることで、企業の取り組みにおいて独自性が抑えられてしまう」という指摘もありました。健康経営優良法人制度が画一的な取り組みを推奨するのではなく、各企業の独自の理論、取り組み、成果を評価できる柔軟性を持つことで、制度全体がより豊かで活性化したものになるはずです。
初心者企業へのハードルの高さ
設問数の多さ、必須項目と任意項目の見分けにくさ、専門用語の多用など、健康経営に初めて取り組む企業にとっては非常にとっつきにくい印象を与えています。
調査票自体が健康経営のガイドとして機能するためには、企業の成熟度に応じたマイルストーンの提示が必要ではないでしょうか。例えば:
- スタートアップ段階:最低限クリアすべき項目と基本的な取り組み
- 成長段階:効果測定や改善サイクルの確立
- 成熟段階:グループ企業展開や先進的な取り組み
このような段階的なアプローチを示すことで、どの企業も自社のペースで健康経営を推進できるようになるはずです。
来年度に向けて準備すべきこと
1. 早めの準備が成功のカギ
今年度、多くの企業が苦労したのは準備不足でした。7月頃から以下の準備を始めることをお勧めします:
- 調査票の変更点の早期把握
- 必要データの洗い出しと収集方法の確立
- 関係部署との調整スケジュールの策定
2. データ管理体制の構築
「あのデータどこにあったっけ?」「去年の数値が見つからない」という声をよく聞きました。健康経営に関わるデータを一元管理できる体制づくりが急務です。健康管理システムの活用も一つの解決策となるでしょう。
3. 経営層との連携強化
今年度の調査で明確になったのは、健康経営は人事部門だけでは完結しないということです。以下の点で経営層との連携を強化しましょう:
- 健康経営の目標(KGI)設定への経営層の参画
- 定期的な進捗報告の仕組みづくり
- 投資対効果の可視化
4. 目標レベルの明確化
「ホワイト500を目指すのか」「とりあえず認定が取れればいいのか」によって、必要な工数は大きく変わります。まず自社がどのレベルを目指すのかを明確にし、それに応じたリソース配分を行いましょう。
最後に
令和7年度の健康経営度調査は、これまでと比較して設問の難易度が確かに上がりました。しかし、これは健康経営が「やっているフリ」から「本当に効果のある取り組み」へと進化している証でもあります。
今回の振り返りを通じて見えてきたのは、健康経営が真の意味で経営戦略と一体化させていくことが求められているということです。KGI設定による戦略の明確化、経営層の実質的な関与、グループ全体での展開など、すべてが「担当者レベルの健康経営」から「企業全体を巻き込んだ健康”経営”」への転換を示しています。
一方で、企業規模や業種による格差、新指標の実務での活用方法、初心者企業への配慮など、制度設計上の課題も明らかになりました。これらは健康経営を日本全体に広げていく上で、避けて通れない課題といえます。
健康経営は長期的な取り組みであり、一年で完璧を目指す必要はありません。また調査票を網羅していくことも健康経営の本旨からは外れてしまいます。自社のペースで、できることから着実に積み重ねていく。そして何より、経営理念を達成するためにも従業員の健康と幸福を真剣に考えた経営姿勢を持ち続けることが、最も大切です。
とはいえ、健康経営優良法人の取得も一つの重要な成果であり、今年十分に対応できなかった場合には、今から準備を始めれば必ず今年度より良い結果につながるはずです。健康経営の道のりは続きますが、一歩一歩、確実に前進していきましょう。
執筆・監修
WellaboSWP編集チーム
「機能する産業保健の提供」をコンセプトとして、健康管理、健康経営を一気通貫して支えてきたメディヴァ保健事業部産業保健チームの経験やノウハウをご紹介している。WellaboSWP編集チームは、主にコンサルタントと産業医・保健師などの専門職で構成されている。株式会社メディヴァの健康経営推進チームに参画している者も所属している。