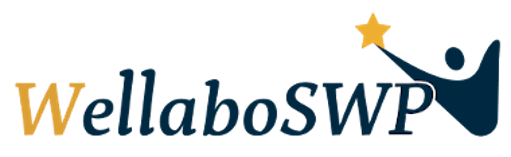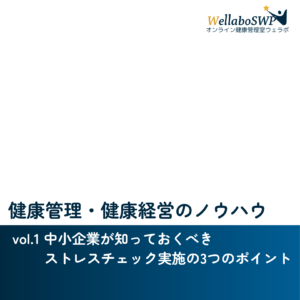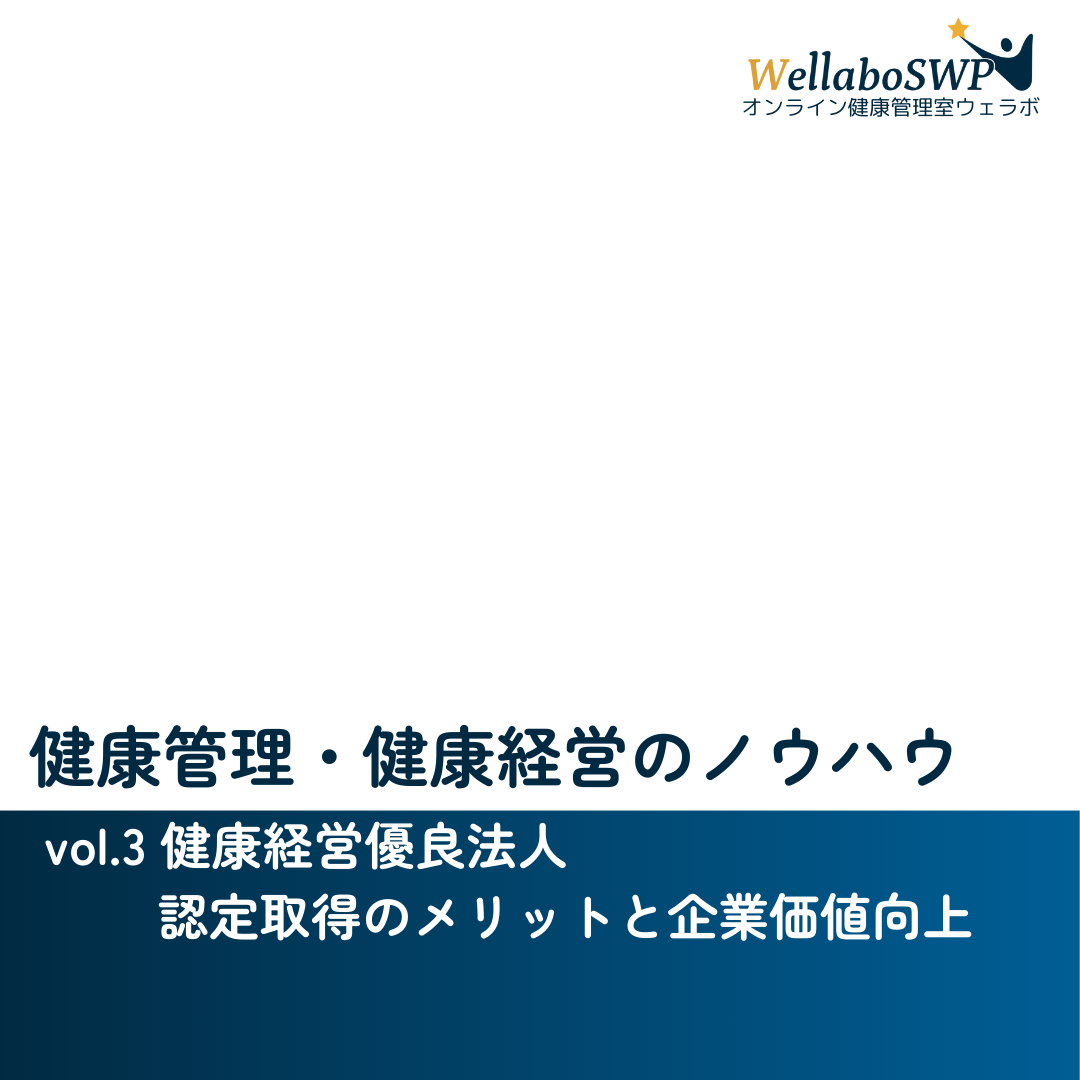コンサルタントが考える健康経営に役立つ健康管理システムの選び方
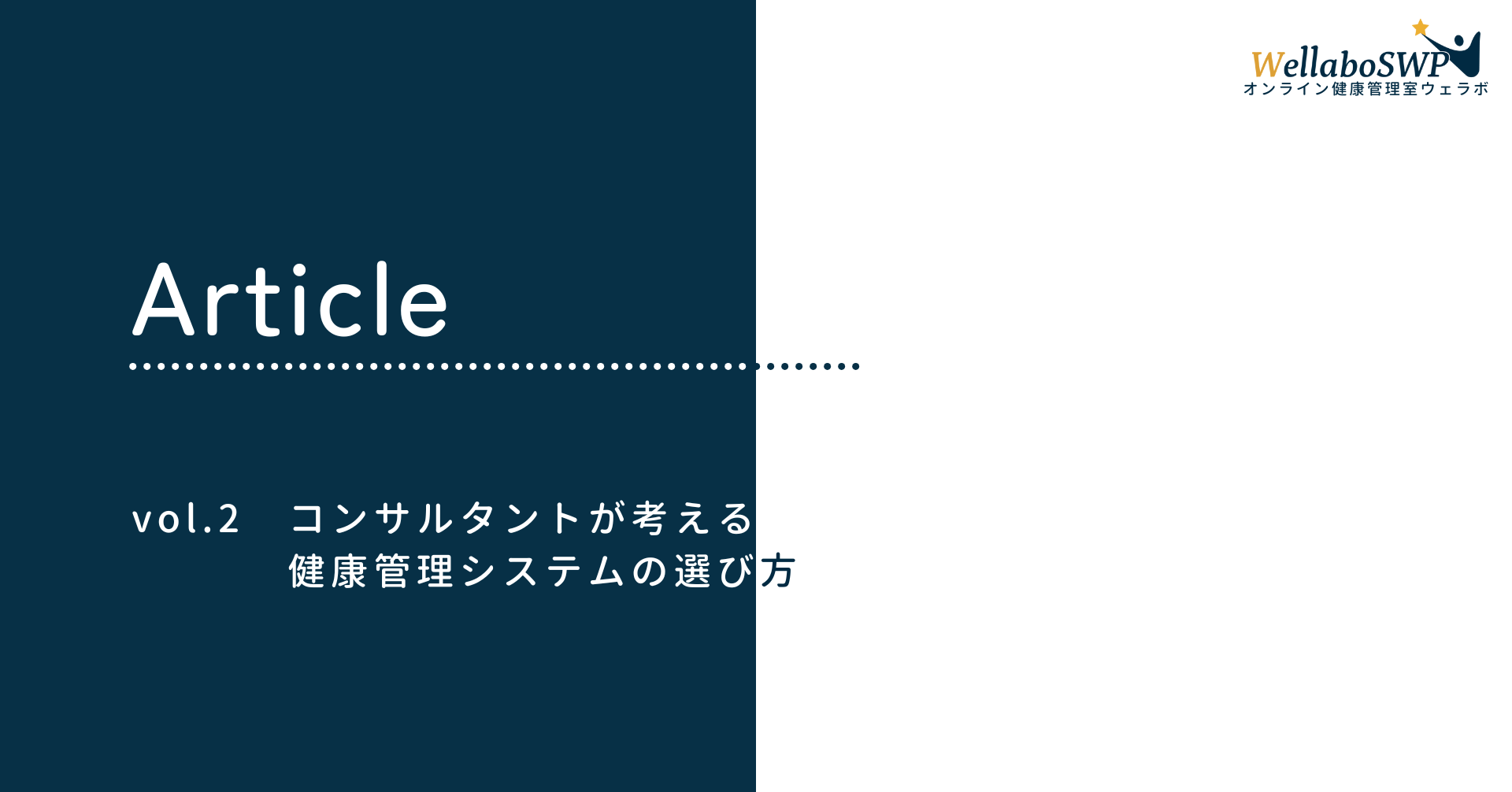
最終更新日:2025年7月9日
「健康管理システムを導入したけど、使いこなせていない…」
「高い費用を払ったのに、結局Excelの方が使いやすい…」
そんな後悔の声を、私たちは数多く聞いてきました。
2025年3月発表の令和6年度健康経営優良法人では、大規模法人部門で3,869社、中小規模法人部門で20,267社が認定を受けました。健康経営への関心の高まりとともに、健康管理システムの導入を検討する企業も急増していますが、残念ながら「導入してよかった」と心から言える企業ばかりではありません。
私たちは10年以上、100社を超える企業の健康経営コンサルティングを手がけてきました。その中で見えてきたのは、「機能の豊富さ」や「価格の安さ」だけでシステムを選ぶと必ず失敗するということです。
健康経営を効果的に推進するためには、健康管理の土台が重要です。個人と組織の健康状態を正確に把握し、適切な施策を講じることが不可欠ですが、従来はデータ化・分析・可視化の作業に専門職や担当者が膨大な時間を費やしてきました。健康管理システムは、こうした問題を解決し、企業の健康経営を支える重要なツールとなっています。
本記事では、実際のコンサルティング現場で蓄積した知見をもとに、健康管理システム選定で本当に重要な3つのポイントをお伝えします。
健康管理システム導入の背景と失敗学

なぜ健康管理システムが必要なのか?
変化する健康管理のニーズ
従来の健康管理は「健康診断を受けて、結果を保管する」程度のものでした。しかし現在では、健康経営の推進により、以下のような高度な健康管理が求められています。
戦略的な健康経営の実現
従業員の健康課題を「なんとなく」ではなく、データに基づいて正確に把握し、効果的な施策を立案・実行・評価するPDCAサイクルが必要になりました。
法令遵守と業務効率化の両立
ストレスチェック、長時間労働者面談、健診事後措置など、法的に求められる業務は増加の一途。これらを効率化しながら、健康経営にも取り組む必要があります。
多様な働き方への対応 テレワークやフレックスタイム制の普及により、時間や場所を選ばない健康管理体制の構築が急務となっています。
健康管理システム導入の失敗学
健康管理システムの導入は、適切な選定と運用設計がなければ、期待した効果を得られないばかりか、新たな問題を生み出す原因ともなります。以下では、典型的な失敗パターンを解説します。
失敗パターン1:
「データの箱」に終わるシステム 運用面を十分に考慮せずシステムを選定してしまうと、せっかく導入したシステムが実運用にマッチせず、単にデータを格納するだけの箱になってしまいます。健診データを電子化して保存できても、データを運用できず、施策立案や効果測定のプロセスが設計されていなければ、高価なデータ保管庫となってしまうのです。
失敗パターン2:
コスト最優先がもたらす隠れた負担 初期導入コストや月額費用の安さだけで選んだシステムが、担当者や産業保健職に大きな運用負担をもたらすことがあります。例えば健康診断結果をデータ化するのに3ヶ月以上かかってしまう、データ投入のための項目の並び替えを担当者が実施する負担が大きいなどの問題が生じ、結果的にシステムを導入したら担当者の負担が増大したという事例が散見されています。中には、システムを導入したにも関わらず、紙で運用し最終的な結果のみをシステムに投入しているといった事例もありました。
失敗パターン3:
数値化の弊害 健康状態の安易なスコア化や数値化は、一見すると従業員にとって分かりやすく行動変容に繋げやすいように見えるかもしれませんが、かえって従業員の不安を煽る結果となることがあります。特に、科学的根拠が不十分なスコアリングや、フォローアップ体制が整っていない状態での健康リスク通知は、従業員の健康不安を増大させ、かえって生産性低下を招くことがあります。
これらの失敗を避けるためには、どうすればよいのでしょうか。
コンサルタントが考える選定の3つのポイント

ポイント1:現在の運用フローとの親和性
健康管理システムを導入する際、最も重視すべきポイントの一つが、現在の健康管理業務の運用フローとの親和性です。健康管理システムは、運営会社が想定した運用フローに合わせて構築されていることがほとんどで、想定されていない運用に対しての柔軟性はシステムや運営会社の考え方によって異なります。システムに運用を合わせるのか、または運用にシステムを合わせるのか、さらにシステムに運用を合わせる場合に許容できることとできないことは何かといった観点でシステム選定をすることが重要です。
チェックポイント
- 現行の運用フローへの影響:
現在の健康管理業務の流れをどの程度踏襲できるか、または変更できるか。改修・オプション対応で対応できるのか。 - 運用変更の範囲と影響:
システム導入によってどの業務がどの程度変更されるのか、その影響範囲は明確か。 - 運用構築のサポート体制:
システム提供だけでなく、業務フロー設計から運用定着までをサポートする体制を持っているか。産業保健や健康管理についてどの程度理解や経験があるか。 - コンサルティング能力:
健康管理の専門知識を持ったコンサルタントが、運用の最適化について支援できるか。
システム導入によって、すべての業務をデジタル化できるわけではありません。まずはシステムが想定している業務フローを確認し、何がどのように変更されるのか、あるいは変更する必要があるのかを整理する必要があります。この際、健康管理システムを多用するであろう、健康管理担当者、産業保健職それぞれの業務への影響度を事前に評価することが重要です。
評価のポイントとなるのは、どうすれば導入しようとするシステムを利用できるのかという観点で議論をすることです。「これができないからダメ」「あれができないからダメ」とシステムを評価すると、一向に自社に導入できるシステムが見つかりません。「この部分は今の運用のままだと難しいけれど、クリティカルではなく、このように運用を変えれば負担なくできる」といった文脈で検討することで、従来の運用と比較してより効率的な運用を実現することもできます。また、そのような検討を導入予定システムのサポート部門と一緒に行うことができるかも重要な視点となります。
ポイント2:システム利用のための「準備工数」
健康管理システムを導入された企業様から「システムは使いやすいが、使えるようにするための準備が思ったより大変で手が回らない」「自社でやらなければいけない要求事項が多い」といった声をお伺いすることがあります。この準備とは初期導入だけを指しているのではなく、毎月発生する従業員の異動、組織変更、残業データの取り込みや、健康診断結果を取り込むためのデータ作成などが該当します。
チェックポイント
- データ取り込みの負担:
データの取り込みは誰が担うのか。取り込みに際し必要な作業は何か - 初期設定の複雑さ:
初期設定の平均的な期間と作業内容。初期設定での要求事項は何か - 運用開始までの期間:
開始したい時期に余裕を持って間に合わせるためにも早めに確認をしておく
健康診断結果のデータ取り込みは、健康管理担当者にとって大きな業務負担になることが多いです。この作業が自社担当者の負担になるのか、システムベンダー側がどの程度サポートしてくれるのかは明確にしましょう。例えば紙の健康診断結果のデータ化には、対応可否も含めてどのように対応できるか、健診機関から納品されたデータを、システム取り込みの仕様への変更はどのように対応できるかは必須の確認事項です。
一部のケースでは、健康診断データ化に対応しているものの納期が長く、健診受診から3ヶ月以上経過した後にシステムに反映されることがあります。また、システムが要求するデータに対応するために並び替えやデータ入れ替え作業が複雑であり、その結果担当者レベルで作業が停滞する場合がありますので注意が必要です。
また初期設定や運用開始までの期間の確認も重要です。組織情報や従業員情報の登録方法、各種マスタ設定の複雑さ、他システムとの連携設定などの確認は必須です。特に、組織変更が頻繁にある企業では、組織情報の更新作業が容易かどうかも重要なポイントです。また初期導入にかかる時間=運用開始までの期間となります。システム導入に際し、健康診断事後措置から始めていきたいと考えられることが多く、健診シーズンが近い場合にはどの程度の期間があれば、余裕を持って導入できるのかを早めに確認しておくことをお勧めします。急いで短期間で導入すると、システム利用について担当者、従業員の理解や周知が追いつかず準備不足となり、さまざまな問題が発生することがあり注意が必要です。
ポイント3:システムでやりたいことが障害なく実現できるか
健康経営の文脈における健康管理システム導入の背景には戦略的な健康経営の推進や、足元の健康管理の徹底と効率化、多様な働き方への対応などが考えられ、これらの背景は企業によって異なります。導入をご検討される場合には、システムを利用して実現したいことを明確にし、かつ優先順位をつけて確認するのが良いでしょう。ここではこのような導入背景を実現する上で共通して確認が必要なポイントをお伝えします。
チェックポイント
- データ分析機能の充実度:
自社の健康経営や健康経営度調査で要求されるデータ分析が可能か - 運用サポートとシステム改修への対応:
やりたい分析を実現するための相談ができる体制があるか - ユーザーインターフェースの使いやすさ:
データ蓄積を支える日常業務の負担にならないか - セキュリティ対策:
データを蓄積しても安心なセキュリティ対策が講じられているか
健康経営を実現する上で健康管理システムが有用となる一つのポイントとして、蓄積されたデータを分析し、課題を可視化することです。自社や健康経営度調査が必要とする分析・可視化機能が標準で備わっているかを確認しましょう。健康診断結果だけでなく、ストレスチェック結果や労働時間データなど、複数のデータを組み合わせた分析が可能かどうかも重要なポイントとなります。また、システムで分析できない場合には任意でデータを出力し、分析できるような機能があるかを確認することも重要です。
機能が充実していても、使いにくさや不十分なセキュリティ体制なら意味がありません。機能に使いにくさや遅さがあると、1日の業務の中ではさほど気にならなくても、年にすると大きな損失となり、またデータ投入に手間暇がかかるとデータ投入が十分に行われず、必要な分析ができないこともあるため、可能ならトライアルやデモ環境を利用してみて使いやすさを確認し、セキュリティチェックシートを用意して確認するのが良いでしょう。
まとめ:失敗しないシステム選びのために
健康管理システムの導入は、単なるIT化ではありません。企業の健康経営を支える重要なインフラ整備です。
成功のカギ
- 運用フローとの親和性を最重視する
- 準備工数を事前に正確に把握する
- 実現したいことが本当に可能かを確認する
私たちの経験では、これら3つのポイントを押さえて選定したシステムは、導入後の満足度が格段に高くなります。逆に、機能の豊富さや価格の安さだけで選んだシステムは、導入後に必ず課題が表面化します。健康管理システムの選定は、企業の健康経営を戦略的に推進するための重要な基盤整備であり、データに基づいた効果的な健康施策の立案・実行・評価を可能にします。さらに有効に活用することで担当者や産業保健職の業務を大幅に効率化することができるだけではなく、より標準的で確実な健康管理の運用を実現します。
健康管理システム導入を成功させるためには、「運用への影響」を確認し、必要な「運用サポートが得られるか」、特にシステムだけではなくシステムを利用するための準備のサポートが得られるかを確認し、その上でシステムでやりたいことを実現することができるかが大きなポイントとなります。
お問い合わせ・資料請求
健康管理システム選定でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
10年以上の経験を持つ専門コンサルタントが、貴社に最適なシステム選定をサポートいたします。
執筆・監修
WellaboSWP編集チーム
「機能する産業保健の提供」をコンセプトとして、健康管理、健康経営を一気通貫して支えてきたメディヴァ保健事業部産業保健チームの経験やノウハウをご紹介している。WellaboSWP編集チームは、主にコンサルタントと産業医・保健師などの専門職で構成されている。株式会社メディヴァの健康経営推進チームに参画している者も所属している。